フィンランドのブルー — トーベ・ヤンソン展に行く [アート]

トーベ・ヤンソン/山猫の毛皮をまとった自画像 (1942)
横浜そごうで開催されているトーベ・ヤンソン展に行って来た。
トーベ・ヤンソン (Tove Marika Jansson 1914−2001) はフィンランドの画家でありムーミンの作者であるが、今年は彼女の生誕100年という区切りの年だということで、《ムーミン展》という展覧会が開かれ、東京での会期はすでに終了しているのだそうで、知らないうちに見逃してしまったのは残念である。
今回の《トーベ・ヤンソン展》はそのタイトルの通り、有名アイコンであるムーミンをクローズアップした展示ではなくて、画家トーベ・ヤンソンがメインとなっている。特に日本ではムーミンがあまりに人口に膾炙し過ぎていて作家の名前より勝っているが、そうしたムーミン・フリーク的傾向とはかなり切り口の異なる捉え方がされていて、そうした意図を知らない者にとっては少し意外性も感じられる内容だった。
まず、ムーミンというのは、その連載が始まるずっと前から、トーベのなかで生成されていたキャラクターで、それをコミックスにして評判を得て、さらにイギリスの新聞から依頼を受け、連載を始めたことにより大ヒットとなるのだが、社会に広く認知されていく過程での弊害として、嫉妬をも含む批判とか否定的な意見も出現し (たとえば初期の頃、ムーミンパパがブルジョア的だとか)、途中からコミックスの製作はトーベではなく弟のラルスに引き継がれたこと。そしてムーミンの成功はトーベに対して金銭的な余裕を与えたが、彼女自身のアイデンティティより肥大したイメージとなったムーミンに対して、彼女はおそらく複雑な、つまり一種のコンプレックスを抱いていたのではないかと思える。
ムーミンを完全否定することはもちろんできないのだけれど、でもトーベにとって 「私は私」 であって、ムーミンに従属した私ではないという矜恃である。
ムーミンは彼女のなかで息抜きの時の間から発案された妖精のようなものであって、そのイメージの原型は多分にプリミティヴな意味合いが濃いように感じる。また彼女は常に原寸大でそれを描いていたため、展示されている原画は驚くほど小さい。
劣化を避けるため展示室の照明も暗めに絞ってあるので、かなり見えにくいのが実情だがこれは仕方のないことだろう。
あくまで自分は画家である、ということを前提としていたらしいトーベの油彩画に繁雑に登場するのは、彼女の自画像であり、それはかなり強い自己顕示の発露であることが伝わってくるし、その性格的な強さがはっきりと示されている。
また《GALM》という政治的な風刺雑誌の表紙や挿画が数多く存在していて、それは反戦的なプロパガンダであり、ナチズムへの批判でもあったりして、戦時中の2色刷に制限された造形から感じとれるのはロシア・アヴァンギャルド的な乾いた美学である。
つまり、ムーミンという、特に日本のアニメのイメージからするとホンワカしたようなやさしいキャラクターとは全く対立するような強い意志を彼女に感じてしまって、ちょっとたじろいでしまう。
1940年に当時の彼女の恋人であったとされるサム・ヴァンニの描いた彼女の肖像は毅然とした表情を見せていて、その強い意志を再現しているように見える。
もうひとつ強く感じたのは、時にその初期の絵画作品に共通する、すべての風景を覆いつくすような青の影だ。その画面のどれもが青いフィルターがかけられているような色彩の青ざめた暗さをたたえていて、素朴に考えれば、フィンランドは寒い土地だからともいえるのだが、そのブルーは気候風土によるものでもあるだけでなく、彼女の心象風景をも表現しているように思える。
トーベが生涯の後半のほとんどを一緒に過ごしたトゥーリッキ・ピエティラ (Tuulikki Pietilä 1917−2009) はグラフィック・アーティストであり、ムーミンの立体作品などをトーベと協同で製作している。彼女はこの展示の解説においてもトーベのパートナーというような漠然とした表現で紹介されているが、つまり同性の伴侶であって、トーベのそうしたセクシュアリティがわかれば、ムーミンにおけるスナフキンの性格のぼんやり感に対する焦点も合ってくる。展示室内の動画では、繰り返し〈花のサンフランシスコ〉が流されていたが、スナフキン的アウトローで内閉的な性向がフラワー・ムーヴメントだけで解釈できるわけではない。
また若い頃には男性の恋人 (たとえば前述したサム・ヴァンニ) たちが存在したにもかかわらず、次第に彼女の強い性格が、弱々しい男性を相手とすることに飽き足らなくなりセクシュアリティが変化していったのではないかという推察もあるようだ。
といって、そうしたセクシュアリティだけが作品のすべてをコントロールするわけではないし、人間がそんなに単純な存在であるともいえないが、それを過剰に隠蔽してしまうのも作家の理解を妨げる要因ともなりうる。たとえば江戸川亂步のセクシュアリティなども近年は比較的伏せられる傾向にあるようで、それが亂步にジュヴナイル作品があるからという理由付けなのだとしたら、トーベ・ヤンソンにもムーミンがあるから、ということで同列な感覚の情報操作なのかもしれない。
トーベ・ヤンソンにはルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』への挿画もあって、アリスの挿画としてはオリジナルなジョン・テニエルが有名であるが、それとは全く違ったテイストのアリスで、凶暴な面構えのチェシャキャットとか面白い。唐突な比喩かもしれないが、バッハの無伴奏ヴァイオリンに対するバルトークのそれに似た感触がある。
キャロルの『スナーク狩り』の挿画もあるようで、それは展示にはなかったが、グッズ売場の書籍の中で見かけた。
日本で作られたムーミンのアニメはトーベ・ヤンソンの好みに合わず、否定されたままに終わっているという。このあたりの事情はよく知らないが、彼女の絵画作品を主体とした今回の展示を見て、単純にかわいければよいという日本の風潮とはかなり違うムーミンの実情を知った。
『ムーミン谷の十一月』というムーミンシリーズの最終作においてトーベ・ヤンソンはムーミンが不在の話を書いた。ムーミンはもう帰ってくるかどうかわからない、という状態のままま、彼女はムーミンを終結させる。ムーミンもまた彼女の作り上げた世界の青い霧の中にいるような気がする。
トーベ・ヤンソン展
http://www.asahi.com/event/tove100/
フォートリエ展に行く [アート]

Jean Fautrier
東京ステーションギャラリーで開催されているジャン・フォートリエ展に行ってきた。
東京駅の丸の内北口の赤煉瓦の駅舎の中に東京ステーションギャラリーはある。保存された古い煉瓦壁に真新しくてきれいな今の時代の金属製の構造物が取りつけられていたりして、ちょっと違和感があるけれど、うまく建物を利用した美術館になっている。
ジャン・フォートリエ (Jean Fautrier 1898−1964) はアンフォルメル (informel) というジャンルに属する画家であるが、いままでその作品を見たのはほんの数点であり、ほとんどは Éditions du Regard版の画集 Yves Peyre《Fautrier》で識ったのに過ぎない。
一般的に抽象画 (Art abstrait) という表現があるが、それではあまりに範囲が広汎過ぎて、でもそれらを細分化したジャンルに分け入ってもその違いはよくわからず、「美術検定」 に挑戦しようとでもしなければ永遠にわからないのかもしれない。それはアヴァンギャルドという表現に出会ったとき、何がアヴァンなのかという問いと共通している。
ともかくアンフォルメルはそうした抽象のジャンルではあるのだが、それになぜ至ったかというのがフォートリエを見てぼんやりとわかったような気もする。
展覧会のキャッチコピーは 「絵画なのか」 となっているが、絵画であることは確かでありながら、幾つかのフォートリエの作風の変遷と合わせて考えてみると、テクニックそのものよりも哲学のようなものに主眼があり、でもそうした見方をするべきなのかどうか、少し迷う。それは衒いであったり、ひっかけであったりすることも多いからだ。
フォートリエの初期の具象作品は、すでにその頃から暗くて、それは色彩的な暗さだけでなく精神の暗さを伴っている。暗さはシュルレアリスムに関しても同様に存在した、ヨーロッパを席捲したアフリカ芸術の影響ともいわれるが、その暗さはアフリカの色合いとは違っていて、絵画の喜びみたいなのが伝わって来にくいように思われるし、暗さの質もフランス的でなく、私は東欧の画家を連想してしまった。
裸婦が何点もあるが、異常にぶよぶよとした体型がおおくて、やがてそれらの輪郭はどんどん単純化されていって、子どもの描いた不定型な宇宙人みたいな像に辿りつく。
(この時代について私は、シュルレアリスムを介在して興味を持ち続けているが、大平具彦の著作を読みながらの感想はまだ書きかけのままである。→2013年07月09日ブログ)
花とか野菜や果物、さらに魚といった静物画があるが、それらはすでに 「花というから花なのだろう」 というくらいのレヴェルに下がりつつある。比較的初期の《兎の皮》(1927) はブラ下げられた幾つものウサギの皮を描いているが、これは結果として、後期作品への一種の予兆だったのかもしれない。
絵の具は厚塗りを越えて盛り上がり、絵画の表面を立体的に浮かび上がらせる。盛り上がった絵の具の先が光って見えたりして、その生々しさにフォートリエの仕掛けを見る。
フォートリエで最も有名なのは戦争体験をもとにした 「人質」 というシリーズであるが、頭部 (首) を描いていると思われるそれらは極度に抽象化されていて、単なる楕円形の絵の具の盛り上がりにしかみえない。しかしなぜ抽象化しなければならなかったか、ということを考えることもできる。グロテスクさゆえの抽象化でありながら悲惨さは抽象化されないという際どさへの挑戦ともいえる。
絵画は絵画であり、その拠り処を音楽や哲学に頼るのは本質と外れる。しかしそうしたムーヴメントは数多く存在してきたし存在しているのだろう。
《All Alone》(1957) はそのタイトルが示すようにマル・ウォルドロンの作品に触発されたものだと解説されていた。フォートリエはジャズが好きだったとのことだが、そのジャズの捉え方は、たとえばモーリス・ラヴェルのジャズへのアプローチとは少し違う。もちろん音楽と美術の違いはあるけれど、それ以前の根源的な差である。
上映されていた生前の画家のインタヴューは、ともすると狷介な印象があるが、たとえば彼にユーモアのセンスは存在していたのだろうか。制作時間はそんなにかからないというようなことを語っていたが、そして実際に描いている様子も映されていたけれども、それをそのまま信じるべきなのかどうかわからない。
晩年には、もう何を描いてもテクニック的には同じでありながら理念的には同じでないとでもいうべき状態であって、1959年に描かれた《黒の青》とか《雨》(これは大原美術館所蔵のもの) といった作品の、表層的に表現するのならば、中央に色の絵の具の塊があって、それにいろいろな加工をしたものとしか見えないが、私が最初にフォートリエをとらえたのはまさにそうした単純な唯美主義者的な美学であって、特に《雨》は美しい。
それにしても《黒の青》とは形容矛盾であり、フォートリエのアイロニーが垣間見える。
Regard版の画集は比較的良い印刷ではあるのだが原画には程遠く、暗い厚塗りの盛り上がった絵の具の質感は再現不能である。それはネット上での画像も同じで、実物の持つ重さは取り払われてしまいがちだ。
絵画に限らず、芸術とはできあがった作品そのものが評価すべき対象であって、その過程とか思想性はまた別物であるべきだと思うが、かといって歴史的な側面を考えないと全く異なった感想を持ってしまう可能性もあると、今回のフォートリエを見ながら気がついた。まさに美学的視点だけで見ていた私のような人間も存在するからである。
美術館の外に出るとそこはいつもの東京駅の雑踏で、美術館内の異空間との落差を感じた。実物の作品と対峙していたときに感じた歴史を遡ることへの畏れのようなものは、単なる夢でしかなかったのかもしれなくて、だがそうした感覚を抱ける作品がそんなにあるわけでもない。

東京駅丸の内北口

東京ステーションギャラリー入口

この中に東京ステーションギャラリーがある

フォートリエ展画集。右は Éditions du Regard版《Fautrier》
東京ステーションギャラリーhttp://www.ejrcf.or.jp/gallery/
Yves Peyre/Fautrier ou les Outrages de l'impossible (Les Editions du Regard)
http://www.amazon.fr/Fautrier-Outrages-limpossible-Yves-Peyre/dp/2903370540/ref=sr_1_29?ie=UTF8&qid=1403132734&sr=8-29&keywords=fautrier
日本amazonは現在、例によってとんでもない価格に。

死の花 —— パーカー・フィッツジェラルド [アート]

Parker Fitzgerald/Overgrowth04
《COMMERCIAL PHOTO》の2月号は野村浩司の特集になっていて、彼はCDジャケット写真で有名なフォトグラファーである。残念なことに昨年亡くなった。
木村カエラの写真が私には印象に残っていて、でも記事を読むと8×10のポラロイドを使ったりした撮影があったとのことだ。フィルムカメラを出自としているのでデジタルに移行しつつある時代でもそうした発想があるのだろう。キーワードはフィルムである。撮った後にあまりいじらない。それがフィルムの基本だとも書いてある。
だがこの雑誌の表紙は少し気色の悪い写真で、男と女が抱き合っているのだがどちらも長い髪、そしてその顔が花で隠されているという構図である。
フォトグラファーはパーカー・フィッツジェラルド (Parker Fitzgerald)、この花のアレンジメントをしたのはライリー・メッシーナ (Riley Messina) というフラワー・アーティストで《Overgrowth》というプロジェクトなのだそうだ。
フィッツジェラルドは 「オーガニックな時代を代表する静謐かつ濃厚なイメージ」 とキャッチにもあるように、やや禁欲的で冷たいトーンで知られる。冷たいというのはよそよそしいとか冷酷という意味ではなくて、綿や麻のような天然素材を連想させる清潔感と、薄くブルーのフィルターがかかったようなpaleな色味の印象を言うのだ。
そしてフィッツジェラルドは今年29歳なのだが、彼もまた、フィルム撮影にこだわっているのだという。
《Overgrowth》は多分にメッシーナのディレクションが濃厚のように思えるが、花で隠されているその部分——マスキングされてしまったような顔の部分が別の生き物としての顔のように見えてしまって、異様な雰囲気を感じる。それはコラージュであり、一種のシュルレアリスムであって、花は美しくなくむしろ不穏な存在感を、何らかの主張を持っているようで、それは邪悪なものなのかもしれず、そのトータルな質感が静謐の中に固定されている。
これはオーガニックとかナチュラリズムとかいうのと少し違う位置にあるように私には思えてならない。オーガニックとは、彼のホームグラウンドにしていた《KINFOLK》という雑誌の方向性からたまたま連想されたイメージに過ぎない。それにもはやオーガニックという単語は少し手垢が付き過ぎて変質し始めてはいないだろうか。
〈Overgrowth04〉は、水面に浮かぶ花びら、水の中に潜っている人、暗い水の色を俯瞰で撮った作品で、水面にできた波紋は高速シャッターで拘束されて一瞬の時を永遠に変える。賑やかな水遊びのショットかもしれないのに、固定されたこの風景には音が欠落している。
これはたぶん死の色なのだ。もしフォトグラファーがそうではないといったとしても、私の直感は欺されないようにと警告してくる。
そしてそれは Death and the Flower (Keith Jarrett) というよりBONNIE PINKの evil and flowers に似ていて、さらにいえば evil and flowers とはボードレールの The Flowers of Evil (Les fleurs du mal) のパロディなのだということに突然気がついた。
COMMERCIAL PHOTO 2014年 02月号 (玄光社)
![COMMERCIAL PHOTO (コマーシャル・フォト) 2014年 02月号 [雑誌] COMMERCIAL PHOTO (コマーシャル・フォト) 2014年 02月号 [雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51SBAU8ujoL._SL75_.jpg)
スヌーピー展に行く [アート]

六本木ヒルズの《スヌーピー展》に行ってきました。
もうすでに終了している展覧会なので、事後報告でスミマセン。
スヌーピーは、チャールズ・シュルツの創出したコミックスのキャラで、私なんかの生まれる前からずっと活躍し続けているたぶん世界でもっとも有名なビーグル犬である——というような解説は誰でも知ってるので、ほとんど不要ですね。
スヌーピーというアイコンはあまりにも強大で、本来の《PEANUTS》というコミックから離れて一人歩きしてるけど、《PEANUTS》のストーリーそのものは意外にシニカルで、しかもオトナが出てこないという独特の世界を形成していて、実は、カワイイというような形容とは少し別のポジションを持っている。
でもそれも含めてのスヌーピーです。
今回の展覧会のサブタイトルは、
しあわせは、きみをもっと知ること。
Ever and Never: the art of PEANUTS
となっていて、思わずケイト・ブッシュの《Never for Ever》を連想してしまった私は
変な人?
シュルツの描いた原画が展示されているのだけれど、結構小さいので見にくいという話を伝え聞いていて、でも実際に見たら日本のコミックス原画などよりかなり大きかった。こんなに大きく描いていたのか!とびっくりするくらい。
コミックスの場合、年を経ることによってキャラクターの描写がどんどん変わっていくのが普通で、ごく初期のチャーリー・ブラウンやスヌーピーは後期のよく知られているお馴染みの外見とは随分違うが、初期の頃の、しっかりとした描線で定着されているチャーリーやスヌーピーの存在感は半端じゃなく陶然とするくらいスゴイ。
チャーリーの顔の輪郭は美しい楕円を基本としているのだが、それは本当に美しい曲線で構成されていて、しかもいきなり直接描かれたようにしっかりとしていて、何の迷いもなくアタリの線も見えない。その線は太くて、完璧に美しいのだ。
そして、吹き出しの一文字一文字手書きされたアルファベットもなんでこんなに確信的なのかと思えるほどに揺るぎがない。
スヌーピーは、最初の頃はごく普通のビーグル犬で、後期のように二足歩行もしていないし、ジョー・クールにもフライング・エースにも変身しないし、つまりまだスーパードッグではなかったのだ。
でも初期のほうがいかにも犬らしくて聡明そうで、まだ斜めに構えたところがなくて、
それはアメリカがまだ上向きの時代であったことを示している。
ルーシーも初登場の頃は、今と違う大きな目をしていて、しばらくしてそれは修正されたのだという。
《PEANUTS》のこのくっきりとした描線は、もちろんスヌーピーは最初から今みたいに有名ではなかったので、雑誌などの誌面でその存在感を示すためには必須のものだったろうし、その精緻な線から読み取れる意味も多いように思われる。
それはたとえばミッフィーの原画でもそうだし、最近のだとギャスパール・エ・リサの原画でも同様だが、大メジャーになるための画にはそれ特有の誰にも負けない個性を強く持ち合わせている必要があるのだということがよくわかる。
グッズ売場は夥しい人、人、人で、ライナスの毛布まで売っていたけど (あぁ、買えばよかった)、そんなふうにしてまで消費されていてもシュルツの設定したスヌーピーの本質はずっと変わらずにいる、というようなことが少しは感じとれたのかもしれなかった。
(原画の展示は撮影禁止のため、画像はありません)



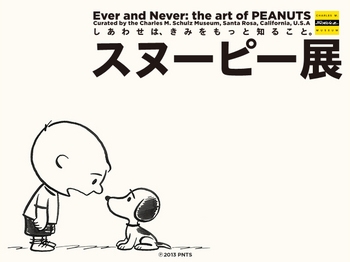

名も無き道の標べに — 美術手帖の特集・横尾忠則 [アート]

横尾忠則 (青森県立美術館ブログより)
『美術手帖』2013年11月号の特集は横尾忠則だった。ヒマな時に興味のあるところを読んでいただけなので、ごくラフな感想に過ぎないのだが、とりとめもなく書いてみようと思う。
横尾忠則という名前は、いわゆるアングラ演劇が流行した頃の、天井桟敷とか状況劇場といった劇団のポスター作品の印象が強烈で、それは横尾色とでもいうべき独特の色彩感覚とレイアウトに支配されている。一度見たら忘れない。
特に強く感じるのは赤で、その真っ赤な 「赤」、つまりプロセスカラーならM100/Y100の、印刷インクでいえば金赤と呼ばれる、もっとも赤っぽい赤である。この雑誌のインタビューなどを読んでいると、横尾は1936年 (昭和11年) 生まれであり、戦争末期の空襲の時に爆撃された火災によって染まる空の赤さがその記憶の根底にあるのではないかと思わされる。
それは恐怖であると同時に、サーチライトに照らされるB29の美しさという記憶として残っているとのことで、赤は〈横尾にとって 「生と死を同時に意味する色」 という赤〉であるとも指摘されている (p.51)。
横尾が5歳の時に描いた絵本の模写というのがあって、この模写はすでにかなり有名なのだが、元絵の宮本武蔵の絵本からの写し方はとても5歳の子どもとは思えないレヴェルである。すべての基本は模写にあると横尾は言う。
ただ、テクニックということを離れてこの絵を見ると、横尾が5歳の時というと昭和16年で、戦争に突入していく頃の日本の空気感というか、そうした剣豪とか、いわゆる英雄譚のもてはやされるテーマが推奨されていた時期だったのだろうということが類推される。
横尾のポスターは、前述の赤を中心とした独特な色彩と、一種のアナクロな造形に満ちていて、そこには繰り返し現れる独特のパターンが存在する。たとえば旭日旗に象徴されるような赤と白の色彩がそうで、旭日旗のパターンはともするとかつての好戦的で右翼的な戦争のシンボルとしての色彩で、それが当時のアンダーグラウンドといわれる演劇のポスターとして、たぶん露悪的に用いられていたという現象が面白い。
最近、韓国などによって旭日旗が当時の日本軍の象徴として排斥されるというニュースがあるが、しかし旭日旗のパターンは、昔の軍隊の旗でもあると同時に朝日新聞の旗でもあって、旭日というパターンは勲章の名称にも存在するようにもっと古来からのパターンであるようにも思える。
つまり赤と白の連鎖は、日本の慶事の際の紅白幕のパターンであり 「ハレ」 の時の色彩であって、梅図かずおの家の外壁だって赤白のストライプである。だからこの赤白というパターンが使われる事象の総体は、その色彩から受けるインパクトによって精神をハイにしてゆくと意味が最も原初的な部分にはあるのだろう。
同時に描かれる花札の絵柄とか古風なフォントなどは、毒々しさ、見せ物小屋の猥雑さに通じ、怪奇譚や冒険活劇を連想させるアイテムであり、なによりもそれは一種の 「様式美」 として作用している。
一度編み出したパターンを拡大再生産することは、つまり模写の思想がその根底にあり、そして繰り返すこととはステロタイプとしての様式美の具現に他ならない。
私が過去の作品の中で最も美しいと感じたのは、1968年の《責場》というシルクスクリーンの作品である。A、B、Cという3枚に分けられ、各2点の、合計6点の絵なのだが、それらはいわゆる版画としての各色の分版であって、それらを重ね合わせた完成形は存在しない。途中の過程だけで終わっている未完成形なのである。
この前、私は、広重や北斎といった浮世絵の再刷りの販売をしているフェアに偶然行き当たったのだが、そこではそれぞれの版が重ね合わされて刷られて、だんだんとかたちになっていく過程が説明されている展示があった。
横尾のはそれに似ているが、彼の原画はおそらくスミの単色だけであり、それに色指定をして各色となって展開しているだけで、浮世絵の刷り師のようなロマンはなくて、もっと機能的である。
機能的であるがゆえに、絵柄そのものは竹に縛られた女性を描いた春画的 (というよりSM的) 題材であるにもかかわらず性的な喚起力は限りなく少ない。それはかつてヴィヴィアン・ウェストウッドがデザインに採用したペニスの連続模様に近い。
横尾を評したキッチュという表現があって、彼はそのキッチュ (Kitsch) さにおいてアンディ・ウォーホルに似ているが、キッチュというのはクレメント・グリーンバーグによればアヴァンギャルドの対義語である。つまり前衛でなく後衛であり、俗悪であって洗練されていないことがキッチュである (ということを、さっき調べていて知った)。
また、当時の美術シーンにおける認識として、こうした横尾の作品が版画であるか、それともデザインであるかという論争があったのだという。すごく簡単に言うならば、版画なら芸術作品だが、デザインだったら使い捨ての消耗品であるという区分けである。
つまりはこの時代、版画にしろデザインにしろ、あるいは芸術にしろ、
それらを峻別してなんら違和感がないくらいにきわめて限定的な、もし
くは曖昧なカテゴライズがまかり通っていたということである。
(p.82/成相肇)
そして、
横尾が、デザインという芸術とは別の、より低価値の領域からやってき
た闖入者とみなされた側面が少なからずあったという背景は確認してお
いていいだろう。(同前)
とも書かれている。
複製されるもの、消費されるものとしてのデザインがあり、デザインとはもともと匿名的なものだ、と横尾自身も述べていたという (p.88)。しかし実際には横尾はブランドとなり、その名前が匿名ではなくなってしまった。それはかつてトゥールーズ=ロートレックやビアズリーが消費財でなくなり、名前が自立したのと似ている。
デザインは受注によって生じるが、芸術は自由で自発的な世界であるという考え方である。
絵を描くことで、受注としてのデザインから、芸術という自由奔放な世
界への脱出の気持ちが止みがたく募り、…… (p.91/松井茂)
その転換により、横尾はデザイナーでなく画家であるという一種の覚醒を得るが、それは 「画家宣言」 と形容されている。
デザインも 「芸術」 であるとする見方にしたがって、横尾のポスターも芸術へと 「格上げ」 され認められることとなった。一方で、本人も自分の作品を 「デザイン」 から 「画家の絵」 へと 「格上げ」 したのだが、その結果はどうなのだろうか。いわゆるカウンター・カルチャーだったものがカウンター・カルチャーでなくなったときという点において、それはタモリに似る。
いまや美術館の島である直島に個人美術館を作った李禹煥 (リ・ウーファン) が、同様の個人美術館を今年 (2013年)、近接する豊島に作った横尾に対して語っているページがある (p.52)。
李禹煥は自分と横尾との相違を語り、でありながら惹かれるもの、共通性をそこに見出しているのだが、彼の作品は 「柱の広場」 に立つ18.5mの高さのコンクリートの柱にも見られるように静謐で緻密な空間である。李もまた、韓国にも日本にもアイデンティティを持ちきれないという故郷喪失者的な精神性において、たとえばナボコフに似る。
一方の横尾の 「豊島横尾館」 は日本の古い民家を元にしているが、すべては日本という風土を感じさせ、そして土俗的で猥雑なテイストを湛えている点では李とは対極にいる。唐突に建っている14mの円柱は、まるでもうすぐ発売されるMacProの形状を連想させるが、その内面は 「滝」 のポストカードで埋めつくされているという。それは2007年の原美術館でのインスタレーションの使い回しであって、横尾の面目躍如な部分でもある。私がポストカードから連想するのは、みうらじゅんだったりするが。それはつまりキッチュの連鎖である。
最後の東野芳明/石子順三疑似対談というページで、松井/成相は横尾の流行に飛びつくミーハーな行動について語り、その後のオカルト的なものへの興味、UFOやピラミッドパワー、ユリ・ゲラー、ノストラダムスといったものとの関連性を印象づける。
「様式美」 をいわばパロディとして始めたことが、その自分の技法自体が様式美となってしまい、次には自分をコピーしなければならなくなったこと、それはもともとの模写→複製という横尾自身の根底にあるシステムなのかもしれないのだが、それが絵画となったとき、その芸術衝動となる元 (コマーシャルなものでなく) が何なのかが不明である。
デザインが芸術となったとき、その猥雑さの表現は深くなったようにも感じられるが、それは有名タレントが大勢いるのに何か空虚だった少し前のdocomoのCMにも似る。
以下は横尾の特集を読みながら考えていた、横尾とは離れた極私的な一般論なのだが、デザインの仕事が匿名性を帯びているということについては、たとえばかつての職人仕事による民芸品や実用品が想起される。それらは無名の作者であり、作者が表面に出ることはけっしてない。びっくりするほどの高値を呼ばないそうした作品のほうが私にはしっくりくる。
そもそも、いわゆるクリエーターとは (アーティストは、という設定でもよい) 「オレがオレが」 とマニフェストしていくものなのだろうか。そして世に名前が出る、有名になるということは何なのだろうか、誰もが自分の名前を世に知らしめたいと思っているのだろうか、というのが私の常に持っている疑問のひとつである。名前なんて単なるシーニュでしかないとする私の考え方は、逆に考えれば冷たいのかもしれない。

横尾忠則/責場 (1968)
美術手帖2013年11月号 (美術出版社)
![美術手帖 2013年 11月号 [雑誌] 美術手帖 2013年 11月号 [雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51pWF9L-mBL._SL75_.jpg)
コラージュとドット — honobono展2013 [アート]

さて、ごくプライベートで身近な話題ですけれど 「PCを捨てよ、町へ出よう」 ということで、ハロウィーンの日に、銀座で開催されている大和田理恵さんというお友達の絵画展に行ってきました。銀座といっても新橋に近いあたりで……って、これじゃ昨年と同じ書き方ですが (昨年の記事は→2012年11月23日ブログ)。
気の合った仲間たちの、今年はひとり増えて7人の展示で、これも昨年書いたことですが、それぞれの個性が違っていてヴァラエティに富んでいます。同じ美大という共通項があるのだとしても、それが継続しているのはすごいことです。継続は力なり。私なんかがここに書いても宣伝にも何もならないとは思うんですが、とりあえずレポートということで。
* * *
今年もメインはデカい作品が2点。そのうちの1点は単純なキャンバスではなくて、真四角な木枠が3×3に分割されていて、さらにその中に小さな絵が2×2になって分散されてハメ込まれている。丸いお皿のような立体も幾つか紛れ込んでいて、全体は標本箱のようでもあり、私はこれを見て 「松花堂弁当」 と言ってしまったが失礼だったかもしれない。でも我ながらすごく的確な比喩なのでここでも使ってしまおう。
絵の表面を覆うドットとか格子模様は彼女のメインツールである。ドットはポルカドットかもしれないし、それともピンホールなのかもしれないが、ともかく覆うこと。昨年の作品ではただ描き込むことでは飽きたらず、実物のネットを絵の表面に付けてしまったが、今年はそこまでには至らないけれど、でもひっそりとあちこちにこの 「覆い」 が存在する。
小さな絵の元となるのはフィールドワークした写真が素材になっていたりして、しかも例えば 「顔のかたちに見える家」 とその前にいる 「自転車に乗った親子」 は2つの絵に分散されていて 「自転車に乗った親子」 はさらに反転した陰画のようになって利用される。
これは一種のコラージュなのだろうか。どんどん分割していくことで、それはつまりPC的な動作表現でいえば、コピペして増殖したものを変形させていることになる。
もうひとつ興味を引くのは、自分の制作過程を写真に撮っておくことによって、だんだんと絵の作成されてゆくのを記録してあることである。それは秘密のノートになって記録されていて (秘密じゃないか)、つまり一種のテンポラリー・ファイルである。
今年の作品は、色が鮮やかで随分描き込まれているように思えるし、絵はどこが完成形かという設問がよくあるが、昨年よりも完成形の終着点が随分後ろになってきたように感じた。
そこで話したことなのだが、たとえば芸術でも音楽とか演劇は1回性の、いわゆる瞬間芸術なところがあってundoが効かない。でも絵画とか文学は制作過程で元に戻ることができる、つまりundoができるとその時は思ったのだけれど、でもそれはやっぱり違う。
色が気に入らないと気づいて、ある色の上に違う色を乗せていくと下の色は隠せるのだが、でもそれは上に塗った色を1色だけでただ塗るのとは違うし、その厚みを最初から出そうとする技法もある。
ということは、実は絵画だってその消費される進行過程の時間軸はlinearでしかなくて、絵を描くということも不可逆性なのだ。デジタルで描いた場合しかundoはありえない。
では文学ではundoが効くのだろうか。私が考えていた小説——というより一種のメモワールのようなものとしての技法なのだが、ひとつの時点におけるイメージを書いておき、ある程度時間が経ったところで、そのことについて回想したことをまた書くことによって、自分の目から見ればそこに時間の重層化が起こる。ただそれは極私的なシステムでしかなくて他の読者には認識できないので、それを普遍化できないかということなのだ。これは私なりの自動記述で、シュルレアリスムの自動記述とはたぶん違うと思う。
そして文学作品の終わりがどこかというと、それは書籍として定着させてしまうというのがひとつの帰結点だが、それを曖昧にしてしまうのがこうしたネット上のテキストデータであったりする。私はこのブログでも後からこっそりと少しずつ訂正したりしていて決定稿というのは永遠に存在しない。その、文学作品が重層的であって完成形が無いのではないか、と思わせるのが校本宮澤賢治全集であって、それはバームクーヘンのような地層の重なりで成り立っている。
音楽の場合、たとえばビートルズの《レット・イット・ビー/ネイキッド》のようにundoが効くようにも思える。だが、幾ら元のトラックからあらたなミキシングが可能だとしても、ミキシングする時期が異なっているのだから真実のundoはやはり得られないことになる。というようなことを私はぼんやりと考えていた。
つまり私たちの乗っているこの歴史という時間はundoができないという平凡な結論に達してしまうのである。何かだんだんと本来の絵画展のことから離れていくなぁ。
ということでお知り合いのかたも、そうじゃない人も是非行ってみましょう。絶賛開催中です。

honobono展
2013年10月29日(火)〜11月4日(月)
11:00〜19:00 (最終日15:00まで)
月光荘こんぱる画室
東京都中央区銀座8-7-5 金春ビル4F
画室直通 TEL: 03-3571-1116 (会期中のみ)
空虚なヴィジョン — ニコラ・ド・スタールに関するメモ [アート]

幾つか前のブログで大平具彦のことを書いたとき (→2013年07月09日ブログ)、その冒頭にサンクトペテルブルク生まれの画家、ニコラ・ド・スタールのことに触れておいた。その後も彼への興味ばかりが膨れあがるのだが、あまりに知識が無さ過ぎるのでまともな内容は書けそうもない。というわけでこれはごく簡単なメモである。
ニコラ・ド・スタール Nicolas de Staël (1914-1955) は画集を見ていて発見した画家である。本とは不思議なもので、強いパワーのある本は向こうからこちらを呼ぶ寄せるのだと思う。「私を飲んで」 というのは不思議の国のアリスだが、本は 「私を買って」 と呼びかけてくるのだ。
ド・スタールはそんなに有名な画家ではないのだろうが私の嗜好にぴったりな画風で、でも最初に連想したのはベルナール・カトラン Bernard Cathelin だった。非常に単純化した具象の絵という点では共通している。
カトランは晩年になるにしたがって、単純化された花瓶に入れた花をテーマに作品を連発した人で、日本では通俗的な意味でかなり有名であり、つまりルノアール的というよりもむしろハローキティ的といったほうが的確かもしれない。私はもっと前の時期のカトランが好きだったが、絵が単純化していくにしたがって興味を失っていった。
ド・スタールはたとえば〈Bateaux〉(1955) のような、ごく単純化された後期の作品がまず引き合いに出されるのではないかと思う。もう少し前だと、ややカラフルな〈Bouteilles〉(1952) のような作品もある。ところが画集をたよりに遡っていくと、初期は厚塗りの暗い印象の抽象画であり、その色と構成力がすばらしい。ここに掲げたのは1946年の〈Composition〉という作品だが、〈Composition〉というタイトルの作品は複数にあって、その年によって集中的に同様の構成の作品が何枚も描かれている。

〈Bateaux〉(1955)

〈Bouteilles〉(1952)

〈Composition〉(1946)
この暗い特殊な色彩感覚と抽象ということから私が連想したのはジャン・フォートリエ Jean Fautrier であったが、フォートリエの抽象は常にひとつの核を持っていて、ド・スタールと違ってそこに収斂しているように見える。
こうしたド・スタールの初期の抽象画は現代の目で見ると、やや古びているが、私が好きなのは何よりその色彩の独特な美しさなのである。そして次第に画風は薄塗りになり単純化されていったが、それによって増幅されたのは寂寞とした何か、というよりむしろ空虚さの滲み出ている全体のトーンである。
単純化の末に到達したド・スタールのこの表現はカトランの至福さとは正反対でしかない。
ド・スタールは貴族の家に生まれたが、しかしすぐにロシア革命が起こりポーランドへ亡命、さらに両親が亡くなりベルギーへ行き養父母に育てられる。モロッコのマラケシュでジャニーヌ・ギユー Jeannine Guillou という人妻と会い、子どももできるが彼女と正式に結婚することはできず、そしてニース、パリと住む場所を変えていったが、絵は売れず、やがて貧しさの中でジャニーヌは亡くなってしまう。
ジャニーヌの死以降、フランソワーズ Françoise Chapouton を妻に迎え、3人の子どもがいるが、彼は憑かれたように絵を描き続ける。その絵の裏側に見えるのは深い悲しみを通り過ぎた、うつろな心情のような気がする。そうした喪失感はなぜ出てきたものなのだろうか。
やがて絵が少しずつ売れ始めた頃、またド・スタールに新たな女性の影がみられるが、精神的に不安定となり絵が描けないという悩みにつきまとわれ、ある日、アトリエのあるビルから飛び降りてしまう。享年41歳であった。
私が参照した本は Marie de Bouchet《Nicolas de Staël/Une Illumination sans précédent》という小冊子と Jean-Claude Marcadé《Nicolas de Staël/Peintures et dessins》だが、Marie de Bouchet という著者はド・スタールとジャニーヌの娘である Anne de Staël の娘、つまりド・スタールの孫である。
Jean-Claude Marcadé/Nicolas de Staël Peintures et dessins (HAZAN)

Marie de Bouchet/Nicolas de Staël Une Illumination sans précédent
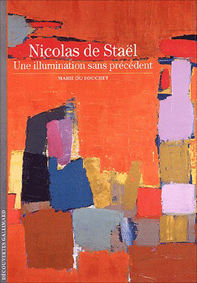
喪失感について — 伊藤正道展・2 [アート]

先日、伊藤正道展 「僕への小さな旅」 に行ったこと (→2013年02月16日ブログ) を書いたが、giogio factoryからそのお礼状のポストカードが送られてきた。〈four apples〉と名付けられた作品が印刷されていて、宛名面にはお姉様が文章を書かれている。あらためて正道氏の急逝が惜しまれる。
絵は淡く濁ったピンクを背景にして、おじいさんと少年が大きな器のようなもののフチに腰掛けていてそれぞれに青いリンゴを持っている。床にはさらに2個、リンゴがある。全部で4個のリンゴ。
絵本『マフィー君とジオじいさん』(2000年) のあとがきで伊藤正道はこの2人について書いている。
ジオじいさんの中にぼくの子ども時代の夢があり、マフィーくんの中に
ぼくの子ども時代の姿があるようです。
ふたりの出かけるのはカラフルなドリームランドでありネバーランドである。ジオじいさんはマフィーくんにとっての遊びの師匠であり、楽園への案内人なのだ。また明日、今度は何して遊ぼうか、その楽しみは尽きない。
もう少し前の作品『三日月の夜』(1997年) では、おじいさんはすでに亡くなっていて、少年は犬のペロと一緒にセロファニア国へ旅に出かける。三日月に向かってどこまでも歩いて行くとセロファニアに辿りつくのだという。
だがなかなか辿りつけないセロファニア。途中で出会うティア・クラウンもピアノ弾きのロボットもなぜか悲しい。その悲しみの黄昏のような雰囲気はカラフルに見えるCD-ROMゲーム〈Cellofania〉にもひっそりと存在していた。
少年 (子ども) もおじいさん (年寄り) も、社会的な目から見れば〈数に入らない世代〉のひとびとだ。伊藤正道はその絵とストーリーの中にこの世界を動かしているはずの一般的な壮年のひとびと (オトナ) を描かない。それはチャールズ・M・シュルツがスヌーピーのコミックスの中で、基本的にオトナをオミットしているのと通じる。
そもそもパーティとかカーニバルとか、そうしたお祭りの後には物憂い悲しみのようなものが澱となって残るものだが、そして絵本に描かれるパラダイスはそうした自分のイマジネーションの具現化であって、その世界へのトリップ感覚が読者をも楽しませるのだろうけれど、でもそうした喧噪が静まってからの、アフター・アワーズの悲しみと伊藤正道の淋しさは少し異なるようだ。
ハイになるような喧噪も狂奔もなくて、そのかわりにずっと持続している通奏低音のような淋しさの音があって、それが私には喪失感のようなイメージとして感じられてくる。
〈four apples〉の床にころがっている2個のリンゴの持ち主は誰なのか。それとも持ち主は不在なのだろうか。このポストカードの絵からもっと色々なことを考えたのだが、あえて書かないことにする。
伊藤正道/マフィーくんとジオじいさん (小学館)

伊藤正道/三日月の夜 (ART BOXインターナショナル)

伊藤正道展 「僕への小さな旅」 に行く [アート]

伊藤正道公式サイトより
冷たい雨の夕方、恵比寿に伊藤正道展を観に行ってきた。
画廊は恵比寿の駅からすぐのしっとりと濡れている小路にあって、看板にはもう照明が点いていた。
伊藤正道の作品は、ほんわかとしたタッチの絵で、その名前を知らなくてもきっとどこかで見た覚えがあるのではないかと思う。カラフルだけれど柔らかくて、そしてちょっとだけいつも淋しさが垣間見えるような、そんな画風である。
だが彼は昨年急逝した。病気だった母親が亡くなって、すぐ後を追うようにして亡くなったのである。私は同様だったアレクサンダー・マックイーンの悲報の時を思い出した。
私が最初に伊藤正道と出会ったのは、おそらく初期の頃のMacのCD-ROMゲーム《セロファニア》のキャラクターデザインだと思う。今から考えればごく初歩的な動作しかしないゲームなのだが、きっとその裏に秘められたかたちにあらわれないイメージを読み取っていたのだと思う。当時のゲームで印象に残っているのは、この《セロファニア》と、たむらしげるの《ファンタスマゴリア》、そしてシナジー幾何学の《ガジェット》あたりだろう。



伊藤正道にとっての重要なテーマは少年とおじいさんである。それはつまりひとりの人間の歴史の象徴であり、過去から現在を抜けて未来へと続く 「時」 を現している。
「僕への小さな旅」 は絵本の原画で、キャンバスにアクリル絵の具で描かれているが、その空の色は微妙に冷たくて、時に悲しいように見えてしまう。そしてなぜかちょっとだけ何かが、つまりアイテムが足りないように思える。描かれるはずだったものが省略されているような喪失感 —— これはたまたま作者が亡くなってしまったから、悲しみの色をそこに見てしまうのだろうか。
決してそれは見る者の気のせいではなくて、別に自分の死期を知っていたのではないのだが、何かそこに一種の予感のようなものが現れてしまったのではないかというふうに私はとらえる。そんなふうに、空の色というのは単純にブルーというだけでなく、もっとずっと深い。
思い返せば 「大きな古時計」 のときにもその淋しさのような印象を感じたような記憶があるが、でもそれは原画から醸し出される雰囲気であって、印刷物になってしまうとその悲しみの色は消えてしまう。それは印刷物のラチチュードの限界なのだろう。
画廊には正道氏のお姉様がいらっしゃって、絵の解説などをしていただいたが、正道氏が誰からも愛されていて慕われていた人であったことが感じられた。絵は品性である。画家本人だけでなく、すべての周囲の状況とか人間関係までがその作品に反映されるように私には思える。

残念なのは絵本『僕への小さな旅』が品切れだということである。再版を待っている読者はたくさんいると思うのだが、良い本に限ってたいがい品切れというのが世の常だ。
今後はもう少し大きな展覧会の開催や常設の美術館、そして画集が望まれることである。作品の中に登場するおじいさんの年齢になる前に亡くなってしまったのが惜しまれるが、きっとあの特徴のあるヘアスタイルの少年が伊藤正道の永遠の姿なのだ。永遠の少年をわたしたちは決して忘れない。
恵比寿での会期は日曜までです。
http://masamichiito.com/

角砂糖の島 — 雨の銀座、honobono展に行く [アート]

〈角砂糖の島〉
連休初日の今日はあいにくの雨。
山野楽器銀座店の前では雑踏の中、ユーミンのベスト盤を大々的に販売していて、エンドレスに流される彼女のヒット曲を聞いていると、まるでバブル期を復活させようとするような執念を感じさせる。レコード会社の思惑は果たして当たるのだろうか。
そんな冬を予感させる寒さの中、銀座で開催されている大和田理恵さんというお友達の絵画展に行ってきた。銀座といっても新橋に近いあたりで4丁目あたりの喧噪からは少し遠ざかっている。
気の合った人たち6人がそれぞれの作品を持ち寄った展示で、こうして並べられてみると、絵というのは個性が明確にわかる表現形態なことがよくわかる。それは抽象的な音楽とか文学に較べると、絵画が視覚という非常に具体的なシステムを媒介として伝えられてくる表現だからだと思う。
大和田理恵さんのメインとなる作品は5点 (または6点?)。もっとも大きい作品は〈角砂糖の島〉(トップ画像) といってほぼ真四角な画面に、上のほうが空、そして白を基調とした中に無数の色模様が細かいテクスチャーの変化を伴って描き込まれている。その絵をほぼ覆うようにしてかけられたネット。
添えられている彼女の解説を読んでみると、
何気ない日常に夢を…
そう、スィートアイランド
この島は、甘い甘い幻想で出来ているのです。
角砂糖で積みあげられた廃墟のような島。
奥へ奥へと入っていくと、白い宮殿が現れます。
薄暗い大広間の天井には、無数の小さな穴が開き、
そこから太陽の光が差し込むと、一面がピンホールの海と化すのです。
そこに戯れる、かわいらしい少女たち…
幻想的で、はかなくて
いつ終わるとも分からない、果てしないこの世界。
最近の日本のスイーツブームは考えようによっては飽食の世界の一環であり、つまり溶けやすい角砂糖で作られたような危うい世界であって、なによりそこは廃墟の島なのだという。だから宮殿の豪華でなくてはいけないはずの大広間の天井も、実はピンホールだらけの、死んでしまった建築物なのだろう。
その島に住むためには 「プチモビ」 を着なくてはならないのだそうだ。プチモビとはプチ・モビルスーツの略で、それは入口に飾られた半立体の作品である。ハンガーで吊された 「角砂糖の島」 用のモビルスーツ。下には黒いタイツも付属している。その前にある2個のクッションのようなものは〈PARTS〉という名称の作品なのだそうだが、〈プチモビ〉と〈PARTS〉が組み合わさって集合的なひとつの作品となっているようである。脚にからまるブルーのもやもやはマグリットのようで、クッションの遠近法の構築性はデルボーを連想させる。

〈プチモビ〉
一番の注目点は〈角砂糖の島〉にかけられているネットである。わざわざ自分で編んだという、ところどころ編み目の歪んでいるネット。白いネットは白を基調とした背景に溶け、あるいは青の背景を遮り、一種の怠いモアレのようにも見える。
作者によれば、ひらひらさせて絵とネットの間に見る者を入り込ませる、ネットの中に包まれるイメージがあるのだという。それは肯定的に考えれば暖かで幸福なハンモックのようなものかもしれないが、世界に自分の体がからめとられるという否定的なイメージも内包しているのではないだろうか。
白い部分に細かく描き込まれた種々のドットは、つまり崩壊への不安を孕むピンホールであり、それゆえに不安定で、たとえば中西夏之のようなテクスチャーの美学には決して向かわないように見える。
甘い幻想、甘い夢とは言葉の綾であって、この飽食した我が国に跋扈する幻想/夢と錯覚しうるものはどこかで精算されるべき時期を迎えているのかもしれないが、そうした不安感がキャンバスの平面だけに留まらないで、絵画に立体の要素を付け加える情動となっているのではないかと思う。
帰り道、相変わらず繰り返し流されているユーミンには 「守ってあげたい」 という曲があって、それは安楽な幸せを約束する母性本能の発露のようでもあるけれど、逆に真実に辿りつかないように目の前に覆われる巨大な網なのかもしれないと思いついたのは、この作品から類推して湧き出た考えである。
そう。まさに 「角砂糖の島は、実はこの日常そのものなのです」 ということなのだ。

honobono展
2012年11月20日(火)〜26日(月)
11:30〜20:30 (最終日15:00まで)
月光荘こんぱる画室
東京都中央区銀座8-7-5 金春ビル4F
画室直通 TEL: 03-3571-1116 (会期中のみ)
尚、作品の画像の無断転載をお断り致します。



