ビョークの語る《fossora》 [音楽]
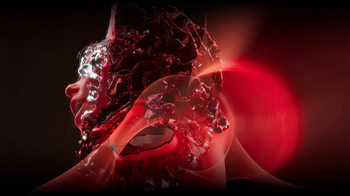
Björk
『Sound & Recording Magazine』12月号にビョークのインタヴュー記事が掲載されている。最新アルバム《fossora》について、幾つか前の記事に簡単に書いただけだったので今回はそのつづき。
インタヴュー記事に先だって次のような記述がある。
収録曲の大半が、一聴しただけでは “曲の骨組み” を読み取れぬほど複
雑であり、セリエル音楽のようにも教会音楽のようにも、はたまたアヴ
ァンギャルドなテクノのようにも感じられる。(p.016)
まさにその通りでもあるのだが、セリーのように無機質で人間的体感が乏しいものではなく、パトリシア・コパチンスカヤなどと同じで、むしろもっと土俗的なプリミティヴさがビョークの音楽の根底に流れている。そうした整合性の無いところから立ち上がって来た素朴な抒情を、しかしながら素直にそのまま受け取ることができないのがビョークの手練れの手法であり特質でもある。
ビョークは 「誰にだって、心の中にコード・ストラクチャーや音楽の景色があると思う」 と、さらりと言ってのけるのだが、ほとんどの一般的な人間の場合、それは意識下に存在する無秩序で発展性のない断片的情動に過ぎなくて、それを組織的に構築し組み上げるだけの音楽的素養が無いのだ。
このアルバムの特徴としてクワイア (choir)、つまりコーラス的な人声の使用があげられる。ビョークは以前から親しかったアイスランドの合唱団ハムラリッド・クワイアから非常にインスパイアされたと語り、「合唱音楽では特定のコード・ストラクチャーが使われる」 ので、自分なりの方法でその世界に入って行きたかったともいう。
〈sorrowful soil〉の不思議な響きについては、3つの3声のグループによる9声のハーモニーなのだが、音がぶつかり合ってしまい、リハーサルに3ヵ月を要したのだという。
インタヴューアーは最後に、「70〜80年代頃の日本のシティポップが再評価されているが関心はありますか」 と訊ねたが、ビョークは表現は柔らかいのだけれど 「よく知らない」 と、にべもない。もし 「知っているし、よく聴いてる」 などと答えられたらかえって怖い。
ベルガー・ソリソンはアルバム《fossora》のミュージック・ディレクターであるが、5年前のアルバム《Utopia》(2017) ではエンジニアを担当していた人で、今回のアルバムでは 「音楽の中で起こっているすべてのことの仲介役」、つまり音楽上のマネージャーであるとのことだが、今回のアルバムのミキシングを担当したヘバ・カドリーと同様、基本的にエンジニアであって、主たるプロデュースはビョーク自身であると考えてよい。
今回の記事を読みながら思ったのだが、ビョークの曲作りは 「試行錯誤の末にできあがった」 といった類いの作り方ではなくて、最初から彼女には完成形が見えているのではないだろうか。その完成形になるべく近く到達できるようにスタッフを誘導してゆくという方法論なのだろうと想像できる。
ヘバ・カドリーは今回のアルバムのミキシングを担当した人だが、本来の仕事はマスタリングであり、今でも自分のことをミキシング・エンジニアとは思っていないとのことである。雑誌後半にあるThe Choice Is Yoursという記事を連載している原雅明によれば、ビョークはブルックリンのTri Angleというレーベルの音を気に入っていて、その大半をマスタリングしていたカドリーにいきなりミキシングを依頼したのだという。しかしカドリーは自分はミキシングはやらない、ある程度の音源データをまとめたステム・ミックスなら扱えると言ってビョークも了承した。カドリーは最終的なミックスを担当するエンジニアがいると思っていたのだという。「ところがビョークは、最初からカドリーにミックスを担当させるつもりだったのだ」 とのことで、結局、カドリーは今回のアルバムではミキシングとマスタリングの両方を担当したのである。つまりカドリーの才能を見抜いたビョークのムチャ振りと考えることができる。
カドリーはDAWはProToolsでなくSequoiaを使用していて、ソリソンはカドリーに合わせて途中からメインのDAWをSequoiaにシフトしたのだそうだ。彼女は坂本龍一の《B-2 Unit》(1980) の2019年のリマスタリングも手がけている。
アナログのマスタリングに関してカドリーの説明がある。
アナログ用のマスタリングは、CDやストリーミングのそれとはかなり
違う。あまりコンプレッションしないし、高域を抑え、低域をよりち密
にコントロールするから。クリッピングしたアタック成分や過度にリミ
ッターのかかったマスターは、アナログ盤だとかなり鈍い音になってし
まうので、ピークを殺さないことでカッティング・マシンの調整幅が広
がり、より良い形にできる。(p.030)
とのことだが、そういうものなのかと納得するしかない。マスタリングの際、プリマスターのバランスが崩壊しているような場合は私がマスタリングで再構築するとも述べているが、そのミックスにオーダーする側が満足しているのならばマスタリングでの作り直しは必要ないとも (シビアな言い方ですね)。
ビョーク特集ページの前には、超アヴァンギャルドともいえるビョークのファッション・ショットが何枚か各1ページ大で掲載されていて、YOASOBIのときもそうだったが、時代の流れの変化を感じる。
今、YouTubeのBjörk BRで昨年のアイスランドにおける 「björk orkestral」 のライヴを観ることができるが、おそろしく長いのでまだ全部観ていない (下記リンク参照)。だが、オーケストラをバックに歌われる〈Bachelorette〉の悲しみに心うたれる。そしてその後の曲〈Pluto〉のイントロのランダムに突き刺さる弦の美しさを聴いて欲しい。

Heba Kadry
Sound & Recording Magazine 2022年12月号
(リットーミュージック)

björk/fossora (One Little Independent)

Björk/Blissing Me (Utopia Live)
https://www.youtube.com/watch?v=u73TNeT2jSY
Björk/Sorrowful Soil
https://www.youtube.com/watch?v=OxvI42YwUfM
Björk/björk orkestral: live
https://www.youtube.com/watch?v=sUbTF0Dc2bo




>土俗的なプリミティヴさ
このニュアンスが色濃いところがビョークを圧倒的に個性的にしているような気がします。音的に「流行」とか「最新」とかいう要素もなくはないですが、しかしそうした風潮とは一切関係なく敢然として存在するビョークならではの世界。
今回、アイスランドの合唱団にインスパイアされたということですが、そしてわたしには大雑把なアイスランドのイメージしかないけれど、その独特な風土とビョークの音楽は切っても切れない関係なのではないかと想像します。スカンジナビア諸国やデンマークと大きく異なる風土ですね。
日本のシティポップについて一応尋ねてるのがすごいですね(笑)。「凄く大好き。とても影響を受けてます」とか答えたら、それこそ一番の衝撃になったところです(笑)。
動画、これからじっくり視聴させていただきます。
「The Beatles/CIRCUS KRONE-BAU MUNICH
Live」、視聴させていただきました。とても興味深い動画です。
ビートルズを詳しく聴いてきたわけではないので演奏能力の高さにはあらためて驚かされますが、観客の雰囲気も日本とはまた違ったものがある点もおもしろいですね。ネクタイした男性も多く来場しています。一週間後に日本公演だったというのも凄い。そして(現在のファンにはこの曲たちで)と見極めての選曲でもあったのですね。
日本ではビートルズ初来日が伝説的エピソードとなっていますが、当時はベンチャーズの方が一般的人気はずっと上で、ビートルズファンは少数派であったとも伝わっています。それがいつしか初来日伝説のようになったのは、もちろんその後のビートルズが比較の対象がないほど巨大になったからでしょうが、外国文化受容史を考える上でもおもしろいです。ベンチャーズについてはどのようなご感想をお持ちでしょうか。 RUKO
by 末尾ルコ(アルベール) (2022-11-06 08:40)
>> 末尾ルコ(アルベール)様
ビョークは普通のロック/ポップスというジャンルでとらえるのが
むずかしくなっているのかもしれません。
独特で特殊な音楽になりつつあるようにも思いますが
だからといってワールドミュージックではないので、
オルタナなロックとでも言ったらよいのでしょうか。
そう言い切ってしまっていいのかも迷います。
アイスランドは地勢的にもいわゆる孤島ですし、
地図で見るとこんなところにあるのか、と驚くような
ポツンと存在している様相に不思議な雰囲気を感じます。
周囲の島々からも取り残されているように単独で存在していて
神の摂理のようにも思えます。
そうした土地で生成された音楽というニュアンスもあり、
まして今回のアルバムはコロナで閉じ込められた
という状況のなかで生まれた経緯があります。
ヘバ・カドリーという人は今回のアルバムの音作りを
総括的に担当していると思われますが、
彼女の力はかなり大きいようです。
普通の雇われエンジニアとはやや違ったニュアンスで
音楽に対処していると私は感じています。
ビートルズの当時のライヴ映像は混沌とした状況を
映し出していることがありますが、
その熱気は現代には無いものなので衝撃的ですね。
ベンチャーズとビートルズの違いは
簡単にいえばベンチャーズはインストゥルメンタルで
ビートルズはヴォーカルのあるバンドということですが、
当時のエレキブームというのは誰もがギターを買って
やってみるという状態ですから演奏スキルは低いはずです。
ギターを弾きながら歌うというのはかなり高等テクニックで、
でもベンチャーズならとりあえずギターにだけ専念できるので
それでインストゥルメンタルが、まず流行ったのでしょう。
ビートルズはビッグネームになってしまいましたが、
それだけによく研究されている面もあります。
ところがベンチャーズは多分の当時の流行音楽という印象で
いまでは軽く見られている傾向があるようなので、
ビートルズほどには研究されていません。
ベンチャーズはギターの音色に特徴があり、当時の機材で
「この音、どうやって出していたんだろう?」 ということが
よくあります。まだ謎の部分が多いです。
CDの出始めの頃、ベンチャーズの再発CDは音が良くないといって
山下達郎はわざわざ自分でリミックスしたこともありますし、
日本のロック黎明期の人たちは必ず影響を受けているはずです。
渡辺香津美、高中正義、大村憲司など皆、そうです。
昨日のハマ・オカモトのFM番組で
今年一番売れたベースはフェンダーのベースVIだった
というニュースを聞きましたが、これは
今年発売されたビートルズのゲットバック・セッションの映像で
使われていたからなのだと類推できるとのことです。
でも、フェンダー・ベースVIといったら
それを持っている写真がジャケットになっている
ベンチャーズのアルバムがあるんですけれどね〜。
もちろんゲットバックなんかよりずっと昔です。
ある程度、ギターやベースをご存知のかたならば
フェンダー・ベースVIといったら
思い浮かぶのは、まずベンチャーズのはずです。
(厳密にいうとベースVIに関してはいろいろあるんですが、
それは別として、ということで)
by lequiche (2022-11-11 15:06)