真四角な部屋と薪ストーブ — 村上春樹『街とその不確かな壁』その2 [本]
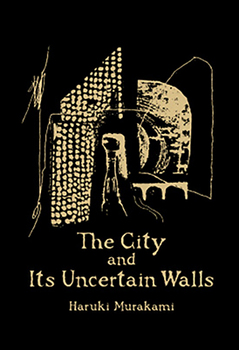
水曜日の子供 — 村上春樹『街とその不確かな壁』その1 (→2023年07月08日ブログ) のつづきです。
この記事は上記作品をすでに読んだ人を対象としています。ネタバレもありますし、読んでいないとわかりにくい個所が存在します。あらかじめご了承ください。
尚、文中の 「私」 は主人公の第一人称として使われている 「私」 です。この記事の筆者のことではありません。また、表記として 「私」 と 「主人公」 が混在していますがご容赦ください。
*************************
第一部で描かれる壁の中の街は、単に電気もガスも無い環境というだけでなく何かが決定的に欠けている世界である。それは現実世界と違う発達をした歴史のようでもあり、スチームパンク的なアナザー・ワールドを連想させるが、そうしたものよりもっと矮小で、ここちよく秘密めいたインティメイトな空間を形成している。
街はさびれていて、その廃絶した状態は何かの疫病があったからではないか、というような暗示もされるが (p.446)、物が足りないこと、不便な生活であること、そして時が止まっているように見えることが主人公である私には一種のユートピアとして認識されているように思える。
並行して進行する過去の物語は、ぼくときみの、名前のない二人がかたち作った壁の中の街の構築過程であり、それは文通という古風な手段を介在して、青春の輝きと悲しみを綴って行くが、砂の城が崩れてゆくように彼女の存在は次第に稀薄になり、やがて消失する。
それは思春期の喪失感であり孤独であるが、主人公はそれをずっと引き摺ったままで年齢を重ねてしまう。
対して第二部は、年齢を重ねた主人公が穴に落ちて壁の中の住人でいようと思ったのにもかかわらず現実世界に戻されてしまったので、壁の中の街の図書館への憧憬から、現実の図書館長となる話である。壁の中の街の図書館で扱われている図書は〈古い夢〉であり、現実の図書館とは異なるが、これはアナロジーであり、幾多の物語が閉じ込められている点において等価である。
第二部のメイン・キャラは主人公である私、子易辰也、イエロー・サブマリンの少年、コーヒーショップの店主であり、死者である子易以外に名前はない。
図書館は福島県にある町だが、壁の中の街のように暗く幻想的ではないけれど、やはり現実から隔離されていて、静謐で、内在された悲しみに満ちているが、これもまた主人公の現実世界におけるユートピアの体現なのかもしれない。
第一部は暗く緻密で幻想的、第二部は明るいけれど決定的な色彩がどこか欠けていて、読みやすい散文的な情緒をたたえながら、その裏側にデーモニッシュな様相が透けて見える。
話から外れてしまうが、この第一部と第二部の関係性から思い出したのは、私が偏愛する作家ジュリアン・グラックの『半島』(La Presqu’île, 1970) であった。同書は3編の作品で構成されているが、冒頭の 「街道」 (La Route) はさびれた過去の街道を行きながら、かつての街道の栄華が去来するという、緻密だがやや晦渋で幻想がダイレクトに理解しにくいような作品であり、動的な 「半島」 と著しい対照をなす。
全く関係性がないように見えて、この対比が重要なのだということに気付いた。それに 「半島」 は動的に見えて実は堂々めぐりで、全く動的ではないのだ。グラックは最後のシュルレアリスム作家といわれているが、この2編はそれぞれ手法が異なりながら、一定の関連性を持っていて、すなわち 「半島」 は 「街道」 を補完することにおいて『街とその不確かな壁』の第一部と第二部の関係性に似ている、と感じたのである。
また壁の中の街で主人公である私が高熱で寝込んだとき、看病してくれた老人が昔、軍人だった頃の、亡霊を見た話 (p.80) や、私が将校で異国で戦闘をしているという幻想的な夢 (p.135) は、戦争がその実体をともなわず、その予感だけがかもしだされていることにおいて、グラックの『シルトの岸辺』や『森のバルコニー』を思い出す。
高校生の頃、通学の電車の中でこの『半島』を読んだ記憶があるのだが、そのときはそこに描かれている内容がよく理解できなくて退屈な印象であった。グラックのおそろしさがわかったのはもう少し後年になってからである。
さて、『街とその不確かな壁』における実体と影との関係から当然連想するのは、アーシュラ・K・ル=グィンの『ゲド戦記』(Earthsea) である (特にオリジナルな最初の3部作)。邦題は順に 「影との戦い」 (A Wizard of Earthsea, 1968)、 「こわれた腕環」 (The Tombs of Atuan, 1971) そして 「さいはての島へ」 (The Farthest Shore, 1972) であるが、原タイトルに沿って、以下 「アースシー」 「アチュアン」 「ショア」 と略することにする (尚、私見だが 「Farthest Shore」 というタイトルはJ・G・バラードの『終着の浜辺』(Terminal Beach, 1964) へのリスペクトのような気がする)。
アースシーにおける重要な命題は名前であり、人には仮の名前と真の名前があって、真の名前を識ることはその者を支配できるパワーを持つことにつながる、というものである。見習いの魔術師であるゲドは、開けてはいけないパンドラの匣を開けてしまったことにより、自分の影に悩まされることになる。この実体と影との関係はル=グィンの『闇の左手』(The Left Hand of Darkness, 1969) における光と影との関係性と同義である。
そして 「アースシー」 で名前の重要性についてあれだけ語られながら、次作の 「アチュアン」 では名前の無い世界を描くというコントラストを見せているのだが、この『街とその不確かな壁』で、名前がほとんど存在しない状態を連想してしまうことも確かだ。
3作目の 「ショア」 は年老いた魔術師ゲドが若者を教える話だが、世界の均衡は崩れ、生者と死者の世界の境界が曖昧になるところは『街とその不確かな壁』のテーマでもあり、その中で引用されるガルシア=マルケスでも同様である (老魔術師が若者を教えるというシチュエーションは《スター・ウォーズ》におけるヨーダとルークの関係性である。ほとんど言及されないが、《スター・ウォーズ》は『ゲド戦記』からの影響が多く存在する)。
ただ『街とその不確かな壁』で描かれる影は、アースシーのような影で暗躍しているような影ではなく、もっと具体的な実体を持っていて、私と影とは会話をし、雄弁な影の強い説得に応じてしまいそうになったりするのだ。
しかし、私と影とが分離している壁の中の街での状態を除けば、影は通常の影であり、したがって影の無い者 (=子易) は死者である。アニメ《となりのトトロ》に於いて、影の無いシーンが死者であることを暗示していると指摘されたのは、影についての定型的な認識である。ということから壁の中の街の人々はすべて死者であるという類推も成り立つ。
壁の中の街の図書館のドアには 「「16」 という数字が刻まれた真鍮のプレート」 (p.28) が付けられているが、16はきみ (=少女) の年齢であり、それは永遠に16歳であり続けることを示しているのだ。壁の中の街の時計には針がない。なぜなら 「時間は進行しない」 (p.634) し、「現在という時しか存在」 (同) しないので、外部からの何らかの働きかけがない限り、私と図書館の少女の関係性は永遠に続くはず、と考えることができる。これが私にとって街がユートピアであるということの所以である。
ところが第一部の終わりで、私が街にとどまりたいと決心したのにもかかわらず現実の世界に戻ってしまったのは、主人公の潜在意識が冥府にとどまることを嫌ったからに他ならない。なぜなら主人公は死者ではなく生者であるからだ。
私は冥府への誘惑にいつもとらわれている。現実世界における冥府の象徴が、魅力的な死者である子易辰也である。つまり子易は、壁の中の街の16歳の少女 (あるいは過去の記憶の中のきみ) のヴァリエーションとも考えられる。なぜ子易がスカートを穿いているのかといえば、子易は憧憬する少女の変形なので、記号論としてスカートを穿かざるをえないのだ。
イエロー・サブマリンの絵が描かれたヨットパーカを着た少年は、現実世界ではコミュニケーション能力に障害があるのに、壁の中の街では私と普通に会話できることからも、少年は本来、冥府に属するべき住人と考えてよい。
第三部で少年は、壁の中の街に違和感を持ってあらわれるが (p.600)、私と一体化することによって、壁の中の住人としてのポジションを得る。
ストーリーの中で緑色は鍵となる色で、少年のあざやかな緑のヨットパーカ (p.600)、第一部で少女が着ているノースリーブの淡い緑色のワンピース (p.10)、壁の中の街で私がかけている濃い緑色の眼鏡 (p.30) など、すべてが緑色で、しかもその濃淡がそれぞれの性格をあらわしているともいえる (これはヴァージニア・ウルフが『灯台へ』(To the Lighthouse, 1927) で用いた色の扱いに通じる。『灯台へ』については→2016年12月03日ブログ、→2016年12月29日ブログを参照)。
少年は壁の中の街に行くため、抜け殻を現実世界に残す。それは私の夢の中にあらわれるのだが、深い森の中の小屋の物置に少年の姿をした人形として捨てられているのだ (p.561)。関係ないかもしれないが (否。関係はないといっていいのだが)、この人形から私が連想したのはバルトークの3大舞台音楽のひとつ《The Wooden Prince》である。3つのなかでは最も有名ではないが、最もアヴァンギャルドな作品である (最近は作品内容から邦題が《木製の王子》でなく《かかし王子》とされていることがほとんどだが 「かかし王子」 は語感が悪いように思う)。
子易がなぜスカートを穿くようになったのか。子易が妻と子を失った後、しばらくして周囲から後妻をという話があったのにもかかわらず、子易はそれを断り、そうした再婚話が来ないように、他人から自分が変な人であると見られるようにと、意図的にベレー帽をかぶりスカートを穿くようになったのが動機だということになっている。
つまり再婚はしないという意思表示でもあるのだが、そこに性的なアプローチに対する拒否が見てとれる。これはコーヒーショップの店主に関しても同様で、彼女はセックスが苦痛でできないこと (p.539)、そして簡単に脱がすことができないような身体を締め付けるオール・イン・ワンの下着をつけてガードしていること (p.581) などによって、性的なものへの拒否をあらわしていると見ることができる。子易のスカートやコーヒーショップ店主の下着が、衣服という記号によって他人を遠ざける意図を示していることはあきらかである。
そしてそうした二人の性的なものへの拒否感は、私の十代の頃にさかのぼって、キスしか許してくれなかった少女に対する性的飢餓感あるいは抑圧へとつながるように思える。
壁の中の街はその不便な環境にもかかわらず主人公にとってユートピアだったのではないか、というのは前述した通りである。街の存在は私、あるいは私と少女によって構築された架空の街に過ぎない (p.126) のだから、自分たちの都合の良いような全体像をとっているのが当然なのである。しかしその世界は狭量で、クエーカー教徒のように禁欲的で、その総体が生きること、ないしは性的欲望から切り離されていることも事実だ。ユートピアでありながらディストピアなのかもしれないという評価も成り立つ。
では現実世界の福島県の図書館での生活はどうだろう。周囲から干渉されることのない、静謐で、コンピュータとは無縁の (図書館では事務処理にパソコンを使用していない)、テレビもオーディオも無い、いわばノスタルジックで前時代的環境。というより禁欲的なことでは壁の中の街のヴァリエーションで、賑やかな生活に対する拒否感が感じられるが、これもまた私の意図によって構築されたユートピアなのかもしれない。
だがそれでいて私は孤独であることが述懐される。川沿いの道を行き止まりまで歩いた先で、
そこに一人で立っていると、私はいつも悲しい気持ちになった。それは
ずいぶん昔に味わった覚えのある、深い悲しみだった。私はその悲しみ
のことをとてもよく覚えていた。それは言葉では説明しようのない、ま
た時とともに消え去ることもない種類の悲しみだ。目に見えない傷を、
目に見えない場所にそっと残していく悲しみだ。目に見えないものを、
いったいどのように扱えばいいのだろう? (p.234)
何がユートピアであり何がディストピアなのか。ここで思い出すのは、やはりル=グィンの『所有せざる人々』(The Dispossessed, 1974) である。資本主義的で享楽的な世界と、原始共産主義的な禁欲的世界を対比させることによって、どちらが人間にとって幸福なのか、ということが提示される。光と影、あるいは実体と影のように二項対立を提示することがル=グィンの常套手段ともいえるが、その世界がユートピアかディストピアかという判断は相対的なものに過ぎず、自らがその世界を創り出したのだとしても、それが自分の理想に合致しているものなのかどうかはわからないのだ。
最後に仄めかされるのは、壁の中の街の少女は、壁が用意した私のためだけの少女かもしれない、ということだ (p.651)。それは子易の存在がなくなった後に、図書館の空気の質が変化したことに似ている (p.505)。
壁の中の街の図書館の新しい〈夢読み〉となったイエロー・サブマリンの少年に対応する少女は、私に対応していた少女とは異なるだろうし、少女でさえ、ないかもしれない。
壁の中の街の図書館の少女は、私のことを知らない。
「いいえ、お会いしたことはないと思います」 と君は答える。君が丁寧な
口調で答えるのはおそらく、君がまだ十六歳のままなのに私はもう十七
歳ではないからだ。(p.31)
同様に、壁の中の街で〈夢読み〉をしている私は、街に出現してきたイエロー・サブマリンの少年を知らない (p.600)。実体と影とは別のものであり、記憶の共有はできていない。
再起動するたびに過去の記憶が消去されてしまうCLAMPの『ちょびっツ』のように、記憶の連続性や、連綿と続く記憶の堆積は無いほうが幸せなのかもしれない。
村上春樹/街とその不確かな壁 (新潮社)





村上春樹は長編はまだあまり読んでないんです。今作も買おうかどうか検討中。読み応えたっぷりありそうですね。村上春樹の長編、やはりどんどん深化していっているのでしょうか。お記事を拝読していると、生と死、そして時間と記憶など、人間にとって最も重要なテーマがより深く掘り下げられている印象を受けます。
実はたまたま現在『レキシントンの幽霊』を読み返しておりまして、こうした短編集で不思議な話を書く村上春樹も魅力です。短編集と言えば『ドライブ・マイ・カー』も読みましたが、素晴らしかった。情念や業といったものも強く感じました。
さらに今作と関係ない話で恐縮ですが、村上春樹の翻訳業の凄さ、レイモンド・カーヴァーやチャンドラー、フィッツジェラルドなどは分かるのですが、最近たまたま古本屋で買ったエルモア・レナードも見れば村上春樹訳。いやはや凄いものです。
凄いと言えばlequiche様、たちどころに共通性のある他の小説が挙がってくるのは凄いです。ジュリアン・グラックもまたじっくり読んでみたいです。
・・・
菅田将暉についてですが、映画ファンの一人として、とにかく「信頼できる頼もしい存在」と思っています。『林修の初耳学』や『SONGS』など、長めのインタヴューをいくつか観ましたが、彼は「常に俳優であり、主戦場は映画である」という印象です。
例えば『SONGS』ではターニングポイントとなった作品として青山真治監督の『共喰い』の映像が紹介されますが、普通地上波では歓迎されないタイプの映画が堂々と紹介されるんです。これは「菅田将暉」というビッグネームであり、そして心底映画を大切に思っている彼だからこその現象だと捉えています。
音楽に関しては、「仕事とは思ってない。プライベートで友人たちとたのしんでいる感覚」であるという趣旨語っていました。これは決して音楽を下に見ているのではなく、(自分はあくまで俳優だから、音楽も仕事と考えると続けられない)ということだと思います。いい考え方ではないかと。
ジャン・ジュネ、本当にそうですよね。近年「作品」に対しても「厳しい姿勢」を取ろうとする傾向があって憂いてます。 RUKO
by 末尾ルコ(アルベール) (2023-07-16 19:18)
>> 末尾ルコ(アルベール)様
買おうかどうか、ということでしたら
しばらくお待ちになったほうがよろしいかと思います。
そのうち文庫本が出るでしょうし、そのほうが廉価ですから。
私は村上春樹のそんなに熱心な読者ではないので、
発売されたらすぐに必ず読むというような
熱心なファン —— いわゆるハルキストではありませんし、
ですから気が向いたときに読むという程度の読者です。
今回のはたまたま読んで、まぁ面白かったかなとは思います。
『レキシントンの幽霊』という本は未読です。
村上春樹は翻訳作業について
小説を書くよりも工程が決まっているのでやっていて楽しい、
気分転換になる、というようなことを書いていました。
すごい余裕ですね。
レコード評などの本も同様なのだと思います。
書くのを楽しんでいるのです。
例にあげた関連書については全く思いつきですし、
グラックなんてたぶん村上春樹は読んでいないと思います。
でもこれは一種の比較文学論と言えなくもないので
見当違いなのかもしれませんが構わないのです。
ル=グィンについては『空飛び猫』を翻訳していますので
アースシーは児童文学の代表作ですし、
おそらく読んでいると思います。
フランス文学で私が偏愛するのは
ジュリアン・グラックとマルグリット・ユルスナール、
あとは……ん〜、ジュール・ヴェルヌとか。(笑)
グラックの 「街道」 は原書で読もうとしましたが
あまりに難しい単語が多くて挫折しました。(-_-;)
グラックはどれか一冊、といわれたら
ありきたりですが『シルトの岸辺』です。
ルコさんは菅田将暉への評価が高いですね。
私はそれほど熱心に映像作品を観ているわけではないので
いろいろと参考になります。
俳優業と音楽との関係、なるほど、思います。
逆にあれもこれも、と均等に興味を持つかたもいるようですが。
by lequiche (2023-07-19 03:24)
第一部は 「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」(1985)や 「1Q84」(2009)と同じく、異なる2つのストーリが並行して交互に進行します。
第二部に名前が出て来たトマス・ピンチョンの 「V.」(1963)もベニー・プロフェイン(三人称視点)の現在とハーバート・ステンシルの過去の物語( 信頼出来ない語り手)が交互に描かれていました。
ピンチョンの 「V.」 に触発されて、リチャード・パワーズが異なる3つのストーリを並行・進行させた長編小説 「舞踏会へ向かう三人の農夫」(1985)を書いたのは有名な話です。
「何曜日に生まれたの」(ABCテレビ 2023)の 「なんうま」 は少年M**のパクリなのかしら?
調べてみたら、「僕」(村上春樹)も 「私」(sknys)も水曜日生まれでした。
(https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/index_20230625.html)
by sknys (2024-02-13 23:16)
>> sknys 様
著者は今回の『街とその不確かな壁』について
『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』では
若書きで描ききれなかったことを書き直してみたい
というようなことを言っていましたが、
2つのストーリーが並行するという方法論は前回を踏襲していて
それはこのパターンが得意というよりも
そのようにしてリベンジするという意味あいもあったと思います。
ただ、私は『世界の終わり……』はとてもリリカルで
著者にとっては不満なのかもしれませんが、
これはこれで良かったし、今の村上ではそのリリシズムは
かえって書けないだろうとも感じます。
また村上は、何かこれは良いと思った使えるエピソードを
ストックしておくとも言っていましたが、
(つまりネタ帳にでも書いておくんでしょうか ^o^)
水曜日の子供もそうした一環かもしれません。
誕生日が何曜日かを表示してくれるサイトもあるんですね。
私は幸いなことに? 水曜日ではありませんでした。
リチャード・パワーズは音楽に対する造詣が深くて
「ここまで知っているのか!」 と驚くことがあり、
とてもスリリングです。
最近の日本は小説にしても音楽にしても
国産偏重主義的な傾向があって、
翻訳小説が以前より読まれにくい環境にあるように感じますが、
パワーズもピンチョンも、まず文庫本を出して
バリバリ読めるようにして欲しいな、とも思います。
by lequiche (2024-02-22 02:58)