椎名林檎《三毒史》 [音楽]

椎名林檎の《三毒史》を聴く。三毒史というタイトルはもちろん三国志のパロディだろうが、そのカバー写真は甲冑を着たペガサスがRDを持っているというメチャクチャさ。中に収められた歌詞のパンフレットは、まるで年代を経たようなシミやヤケが印刷されている。トラックはずっとつながっていて、曲間が無い。
椎名林檎はデビューの頃にはかかさず聴いていたのだが、そのうち人気が出過ぎてしまって、するとワタクシ的には 「まぁいいか」 状態になってしまい、一応買ったり買わなかったり、マジメに聴いたのは久しぶりかもしれない。それはPerfumeも同じことで、あまり人気があるミュージシャンに関しては買わないというのが私の不文律でもあるのだ。だからDMの音楽に関しては、桑田佳祐もドリカムも買わない。だって誰でも知ってるし、いつでも買えるじゃん!
今回の椎名のアルバムのPV〈鶏と蛇と豚〉を見たとき、ん~、まず音がPerfumeだし、つまり声の変調が、そして絵柄は寺山修司だしみたいな、腐敗した風景はグロテスクでありフリークスみたいな絵柄はどうなのかな、でもPV作る人にとってはそういうのが魅力あるんだろうな、とは思うのだけれど。お坊さんのお経みたいなのに対して私は、ズバリ好きじゃない。
最近はカラオケボックスにVT-4を持って行ってPerfume歌うって話も聞くけどホントなのかな。単にローランドの回し者の戯れ言のような気もする (念のためですがホストクラブの人じゃないです)。つまりピッチ変えてフォルマントいじれば面白いのかもしれないけれど、皆、同じ音になってしまうんですよね~、と私は思うのです。そうしたオモチャの音とは根本が違うのかもしれないけど、でも出てくる印象はそんなに変わらない。
般若波羅蜜多と潰れた英語詞の声という傾向から思うのは、つまり声はサウンドであって歌詞を聞かせようとは考えていないのかもしれない。
幸いなことに、結果としてVTみたいな音響は〈鶏と蛇と豚〉と〈長く短い祭〉のみ顕著な特徴で、あとはいつもっぽい林檎節だったわけです。それより今回のは、デュエットというのがコンセプトだったとも言えます。
宮本浩次、櫻井敦司、向井秀徳、トータス松本といった豪華メンバーで、しかもフルバンドの蠱惑みたいなサウンドには痺れる。最後に持ってきたのは齋藤ネコ・コンダクトの〈目抜き通り〉と、そしてヴァーニャ・モネヴァというブルガリアン・コーラス、それにからむアコーディオンが美しい〈あの世の門〉。アコーディオンの背後にひそむルーム感が、なにげなくだけど深い。
サンレコの椎名とエンジニア・井上雨迩のインタヴューによれば、マスタリングしないことというのが今回の録音に用いられたポリシーでありテクニックらしいのだが、その意味がよくわからない。Pro Tools内でのミックスというのが従来のマスタリングとどのように違うのか。でも知ったからってどうなるものでもないのだけれど。私にとってのドキッとする音というのはたとえば〈TOKYO〉の冒頭のピアノだったりする。
今観ることができる映像のなかで、あえてPerfumeな〈長く短い祭〉を選んでみる。これは2018年のアリーナツアー・林檎博’18のものだと思えるが、弦の厚みなどCDの演奏より豪華である。
腕のアクションを多用するダンスは、先日記事にしたミレーヌ・ファルメールのライヴを連想させるが、つまり世界的にこうしたスタイルが流行なのだろうか。同じ曲の2015年の百鬼夜行ライヴもあるが、パフォーマンスの方向性がまるで違う。3年経つとこうなるのかとも思うし、だからそれを進化とするのか、しかし逆にそうしたトレンド感は必ず古びるのだからとも思うし、その刹那感が良いのだとも思う。常に新しい面を拓き、それまでの結果を捨象することで椎名林檎は生き続ける。つまり〈鶏と蛇と豚〉のフリークスは一種のメタファーなのだ。それは単に私の素朴な印象に過ぎないのだが。

*動画リンクは貼れないので適宜検索してください。
椎名林檎/三毒史 (Universal Music)

椎名林檎/RINGO EXPO 18 (Universal Music)
![【Amazon.co.jp限定】(生)林檎博'18-不惑の余裕-【特典:応募ハガキ付】[Blu-ray] 【Amazon.co.jp限定】(生)林檎博'18-不惑の余裕-【特典:応募ハガキ付】[Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/411yleveSxL._SL75_.jpg)
柴田淳 ― 蝶 [音楽]

柴田淳の〈蝶〉は7thアルバム《ゴーストライター》(2009) の5曲目に収録されている曲である。タイトルはゴーストライターだが、別にゴーストライターが書いた曲というわけではなく、全曲柴田淳による作詞作曲である。
歌詞には花と蝶が出てくるが、「花と蝶」 という言葉から連想するのは森進一の〈花と蝶〉(彩木雅夫/川内康範、1968) である。歌詞はいきなり 「花が女か 男が蝶か」 と始まってしまうように、咲いている花と花に寄ってくる蝶を男女関係に喩えているわかりやすい歌詞である。
また、蝶という言葉から思い出すのは木村カエラの〈Butterfly〉(木村カエラ/末光篤、2009) で、これは木村カエラが友人の結婚式用に書いたとされる明るい曲であり、歌詞の最後は 「運命の花を見つけた チョウは青い空を舞う」 となっていて、これも飛んで行く蝶に運命を託した明快な曲である。
一方の花には数多くの曲があると思われるが、私があえて選んでしまうのはSugar Soulの〈悲しみの花に〉(Sugar Soul/朝本浩文・サヨコ、1998) である。〈悲しみの花に〉における花は、
そう 悲しみもやがて
涙色の花に かわるの
という花で、「涙色の花」 にかわるのは 「悲しみ」 であって 「私」 ではない。悲しんでいるのは私なんだから同じじゃん! と感じるかもしれないが、曲の最後は、
あぁ 悲しみはやがて
涙色の花になるでしょう
もう なにも言わないで
こうしていよう あたしがいるよ
と、しめくくられている。この部分を分析すると、涙色の花になった 「悲しみ」 は私が見ている 「悲しみさん」 なのであって、それを冷静に見つめている 「あたし」 が別にいるのである。これはもちろん一種の詭弁なのであるが、「悲しみさん」 を突き放している 「あたし」 の悲しみはより深いのかもしれない。
前のフレーズでは 「涙色の花に かわるの」 と言っているのに、後では 「涙色の花になるでしょう」 と丁寧な表現に変わっているのも諦念のあらわれなのだ。
以上は単なる前フリである。さて、そのような視点で柴田淳の〈蝶〉を読んでいくと、これはもっと屈折していて複雑である。歌詞の冒頭は、
あなたが私にしたことは
忘れてあげない なんて言わない
である。メロディとしては 「あなたが私にしたことは 忘れてあげない」 と歌っておいて、その後に 「なんて言わない」 と付け加える。いきなり出現するこの二重否定に、えっ? と心が動く。しかも 「忘れない」 のではなくて 「忘れてあげない」 のだ。
「忘れてあげる」 のではなくて 「忘れてあげない」 のだけれど、それを 「なんて言わない」 のだから、つまり結論は 「忘れてあげる」 ということなのだが、それを 「あなたが私にしたことは忘れてあげるよ」 と言わずに二重否定を使う屈折度がダークである。そして 「あげる」 という表現にプライドと高慢さがただよう。それは負の高慢さだ。
歌詞のつづきはこうである。
あなたもあなたの存在も
忘れてあげるから
ここで初めてシンプルに、ストレートに 「忘れてあげるから」 と歌う。これは 「忘れてあげない なんて言わない」 の言い換えなのであるが、もちろん二重否定と肯定は同じ意味あいではあるけれど、だからといってニュアンスは同じなのではない。そこに含意が存在するから二重否定なのである。
そしてここにはまた別の屈折がある。「あなたもあなたの存在も」 とあるが、これを額面通りにとらえるならば 「あなた」 と 「あなたの存在」 は別のものなのである。「あなたを忘れてあげる」 だけでなく 「あなたという存在そのものも忘れてあげる」 というダメ押しなのである。
さらに続く歌詞は、
あなたが望むままに 今
つまり 「あなた」 という彼に対して、「あなたは私のことを忘れたがっているのが望みのようだから、私もあなたのことなんか忘れるよ」 とまとめて納得しているのである。恩着せがましいように見えて、実は 「あなた」 はそんなに 「私」 のことを重く思っているわけではないのだけれど、でもそれを 「私」 は認めたくないので、「あなた」 に罪を被せているとも言える。
この最初の5行がこの曲の暗さと屈折度を決定づけている。それが柴田淳であり、それは極端にいえば 「声を聴いただけで悲しい」 彼女の声質の特徴をあらわしている。
さて、歌詞は続いて次のように展開する。
摘み取られるのが花だと知っているの 痛いくらい
忘れ去られた花が どんなに哀しいか
以下は、一種の恨み節であり、内容としては演歌に近いような印象も受けてしまう。ただ、Sugar Soulの 「悲しみの涙色の花」 と同様に、すべては 「花」 に仮託されて、「私」 が哀しいとは一言もいわないのがやはりプライドなのである。
どこかで笑ってるあなたに
踏み潰されもせず
忘れ去られた花のように
は、せめて踏み潰されたのならまだしも、それさえ無く忘れ去られてただ咲いているだけの花という虚無のことである。そして、
もがくほど絡み付く糸を
説く術を身につけた蝶は
と、花の比喩は蝶の比喩にすげ替わる。
歌詞の最後は最初の歌詞のルフランであるが3~4行目が変化する。
あなたが私にしたことは
許してあげない なんて言わない
忘れた花には止まらない
舞い上がる蝶になる
あなたが望むままに 今
忘れ去られた花はすでに死の花なのであるから、そんな花にとまる蝶はいない。しかし、その死の花は 「私」 の過去の姿であり、それを客観的に見つめている 「私」 がいるのである。ではこの後、「私」 に希望があるのかというとそれはほとんど見えない。そうしたダークな風景のままで歌は終わる。花や蝶は、前述した歌の歌詞のように具体的ではなく抽象的だ。花が女で男が蝶だったらわかりやすくていいのに、というような地点がずっと過ぎ去った時代からこの歌は始まっているので、明視性が乏しいのである。
思わず 「時代」 と書いてしまったが、時はそのようにリニアに経過してゆくものであり決して遡行することはない。それゆえに哀しみはそこここにうち捨てられていくものなのである。
柴田淳に惹かれたきっかけは、荒井由実の〈ひこうき雲〉あるいは〈卒業写真〉のカヴァーの古い映像であった。彼女のカヴァーには定評があるが、なによりもその声がすべての曲想を変えてしまう。それは化学反応であり、ときとして虚無という毒を生成する。
柴田淳/ブライニクル (ビクターエンタテインメント)

柴田淳/蝶
https://www.youtube.com/watch?v=v5lzx8mpuE4
柴田淳/Love Letter
https://www.youtube.com/watch?v=jdfNX5TsNfs
柴田淳/それでも来た道
https://www.youtube.com/watch?v=EJCsPXFGW7E
柴田淳+大江千里/卒業写真
https://www.youtube.com/watch?v=kFA3J8lNH18
ペーター・ブロッツマンを聴く [音楽]

Peter Brötzmann (2008)
ペーター・ブロッツマン (Peter Brötzmann, 1941-) はドイツのフリージャズのリード奏者である。主にサックス奏者だがクラリネットも吹く。だがサックスだろうがクラリネットだろうが、極端に言えば皆同じである。メチャクチャ吹いて吹いて吹きまくる。怒濤のように来襲して、ワンパターンで、常にフォルティシモで、音なんてどうだっていいので、楽器が全部無くてもいいので、楽器の下半分をとりあげられて上半分のリードの部分だけになっても、それでも延々と吹き続ける。もう、ほとんどトムとジェリーの世界である。そして吹くだけ吹くと、嵐のように去って行く。
昔からそのスタイルで、全然自分のスタイルを曲げない。フリージャズっていったって、いつでもメチャクチャやっていればいいってもんではなくて、たまには違う方法論があったっていいだろう、と普通なら思う。でもそれが彼には無い。全く無いのである。スタイリッシュとかセンシティヴとか、そういう単語は辞書に存在しない。常にフル・ヴォリュームでVU振り切れるだけ吹けばそれでオッケーなのである。ほとんどバカである。ほとんどというか、もう完全にバカなのかもしれない。
たとえばYouTubeに1974年10月のワルシャワでのライヴ映像がある。クァルテットの演奏で、ピアノはまだ若い頃のアレクサンダー・フォン・シュリッペンバッハである。TVP (Telewizja Polska SA) によるモノクロの映像だが、もう最初から全開である。シュリッペンバッハはさすがに緩急とか強弱を心得ていて、混沌一辺倒でなくリリカルな方向に持って行こうとしたりするが、結局元の木阿弥になる予感を常に秘めている。
ベーシストのペーター・コヴァルトはアルコを多用するが、このメチャクチャな音群の中で正統的な音をキープし続けている。しかしシュリッペンバッハがピアノの中をスティックで叩いたりし始めると、演奏は次の局面に突入するが、ピアノのひとつひとつの音はまだクラスターにはならない。走り続けるブロッツマンに対して、シュリッペンバッハのピアノとパウル・ローフェンスのドラムスの細かい音の応酬がより細分化されたリズムになって降りかかる。
楽器は凶器であり、演奏は時として狂気であるが、そう見えて実はそうではない。メチャクチャのように見えてそこにブロッツマンの音楽構造が透けて見える。でもブロッツマンはきっと言うだろう。「ただ吹きたいだけ吹いてるだけだよ」 と。
1974年がポーランドにとってどういう時代だったかということを思い出さなければならない。それはオイル・ショックの頃であり、PZPRの時代であり、鬱屈の時代である。
たとえば同じ1974年にレコーディングされたアルバムには山下洋輔トリオの《CLAY》がある。ドイツのメルス・ジャズ・フェスティヴァルにおける1974年6月2日のライヴであり、メンバーは山下、坂田明、森山威男であるが、このブロッツマンを聴いてしまうと坂田のアルトのほうがずっとスタイリッシュだ。
同じ1974年にはセシル・テイラーのソロ《Silent Tongues》がある。1974年7月2日、スイスのモントルー・ジャズ・フェスティヴァルにおけるライヴである。その前年、ピアノ・トリオでの日本におけるライヴ《Akisakila》を経てのソロであり、彼の最も充実していた時期である。
つまりそうした時代性を考慮した上でブロッツマンを聴かなければならない。音楽は世界情勢と関係ないようでいて、如実に時代を映すものである。
だが21世紀になってもブロッツマンの演奏は変わらない。相変わらずのフォルティシモ吹きまくりであり、年齢とか時代とか周囲の反応とか、全然考えのうちに入っていないのである。だからやっぱりバカなのである。だが実は、おそろしい静謐の音楽を内包しているのに知らないふりをしているバカなのである。
私はある日の演奏の後で、ブロッツマンから直接サインしてもらったCDを持っている。これはかけがえのない宝物である。
Peter Brötzmann/Brötzmann Box (Jazzwerkstatt)

Peter Brötzmann/Machine Gun (Cien Fuegos) [LP]
![MACHINE GUN [LP] [Analog] MACHINE GUN [LP] [Analog]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51XVWMJ%2BmOL._SL75_.jpg)
Peter Brötzmann Quartet
17. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Jazzowej "Jazz Jamboree"
Poland, October 1974, Warsaw (Sala Kongresowa)
https://www.youtube.com/watch?v=dFa0oyF63d0
Masahiko Satoh, Akira Sakata, Peter Brötzmann
“BrötzFest 2011” Shinjuku Pit Inn
https://www.youtube.com/watch?v=mPGsk1FnhKA
カニグズバーグ『クローディアの秘密』を読む [本]

E. L. Konigsburg
E・L・カニグズバーグ (E. L. Konigsburg, 1930-2013) の『クローディアの秘密』は岩波少年文庫に収録されている有名な児童書だが、家出をしてメトロポリタン美術館に泊まるという面白い発想なのに引き込まれてしまう。
だが ”From the MIxed-up Files of Mrs.Basil E. Frankweiler” が原書のタイトルで、このままのタイトルだったら翻訳書としてはちょっと無理。『クローディアの秘密』と変えたのは鋭い。大貫妙子の〈メトロポリタン美術館〉(1984) という曲は、この小説を元ネタにしていて、NHKの〈みんなのうた〉で繰り返し流されている。〈ピーターラビットとわたし〉と並ぶ大貫妙子のかわいい曲の双璧である。
物語の冒頭、フランクワイラーという人の手紙文で始まるので、これは何? と思うのだが、それは結末で全てが明らかになる。家出という、本来なら暗い題材のはずなのに全然暗くない。その家出の理由というのがつぎのように書かれている。
当のクローディアよりこのわたしにはっきりわかる原因もあったかもし
れません。毎週毎週が同じだということからおこる原因です。クローデ
ィアは、ただオール5のクローディア・キンケイドでいることがいやに
なったのです。(p.11/漢字にふられているルビは省略。以下同)
でも家出をしてみじめな状態になるのは避けたい。だから街の中に隠れてしまおう。クローディアはそう考える。「家出をする」 のではなく 「家出にいく」 というのだ。
クローディアは、町が大すきでした。町は優美で、重要で、その上にい
そがしいところだからです。かくれるには世界でいちばんいいところで
す。(p.13)
クローディアは入念に下調べして、3人いる弟の中で一番信頼できそうなジェイミーを仲間に引き入れて、ヴァイオリンのケースとトランペットのケースに下着を詰め込んで、2人で家出し、メトロポリタン美術館に寝泊まりする。ジェイミーを選んだのは、実はお小遣いを貯め込んでいて一番お金持ちそうだったからでもある。クローディアはもうすぐ12歳、ジェイミーは9歳。ふたりの会話はちょっと生意気だ。
メトロポリタン美術館はたいへんな入場者数で、その小説が書かれた頃は無料。いかにして警備員の目をかわして夜の間、美術館の中にい続けるかというクローディアの知恵が冴える。もっとも今だったら警備用の機器もあるし、こんなことはできるはずがない。そうした可能性が存在していた、のどかな時代だったのである。
家出のプランを主導したのはクローディアだが、お金を管理しているのはジェイミーで、クローディアがタクシーやバスに乗りたがっても、頑として拒否して歩くことを強要される。悪ガキなんだけれど、とても細かくて笑ってしまう。高いレストランには入らず、安そうな店に入って食事をし、昼は美術館に見学に来る小学生の団体にまぎれて、一緒に食事してしまう。
クローディアは家出をしても汚い格好になってしまうのが嫌で、2人は毎日着替え、でもヴァイオリンのケースやトランペットのケースがトランクがわりでは、服は幾らも持って来られなかったので洗濯する。貸洗たく機屋 (コインランドリーのこと) に行ってまとめて洗うと、白い下着がグレーになってしまう。あ~あ。でも、めげない。
噴水をお風呂がわりにして身体を洗っていると、ジェイミーが噴水に投げ入れられたコインを見つけて、しっかり頂戴してしまう。まぁつまり2人は、今だったら細かな犯罪になってしまう 「悪さ」 を重ねているわけだ。
あらゆる種類の上品さのつぎに、クローディアが愛しているのは、よい
清潔なにおいなのです。(p.65)
だが、最近美術館が安く買い入れて特別展示されているミケランジェロの作かもしれないという彫像にクローディアは興味を示し、それを調べるために図書館に行ったりして推理を巡らす。そしてその証拠を発見し匿名の手紙を美術館に出す。そこから話は急展開してフランクワイラーの話につながるのだが、フランクワイラー家を訪ねた2人は、家出をしていることを見破られ、そして2人の家出には終わりがくる。
フランクワイラーが2人を諭す言葉は、単に家に帰りなさいという意味だけでない重層的な意味を伴って聞こえる。82歳のフランクワイラーはクローディアにこう言う。
「冒険はおわったのよ。なんにでもおわりがあるし、なんでもこれでじゅ
うぶんってものはないのよ。あんたがもって歩けるもののほかはね。休
暇で旅行にいくのと同じことよ。休暇で出かけても、その間じゅう写真
ばかりとっていて、うちに帰ったら、友だちに楽しかった証拠を見せよ
うとする、そんな人たちもいるでしょう。立ちどまって、休暇をしみじ
みと心の中に感じて、それをおみやげにしようとしないのよ。」 (p.203)
フランクワイラーが言うのは彫像の真贋がどうなのかとか、それが金銭的にどのくらいの価値があるかなどということは 「もの」 の本質ではないということ。彼女の中でそれが真のものであるのならばそれでいいのだという、一種の諦念でもあるのだ。
さらに彼女はクローディアが、日々新しく勉強しなければならないという意欲に答えて言う。
「いいえ。」 わたしはこたえました。「それには同意できませんよ。あん
た方は勉強すべきよ、もちろん。日によってはうんと勉強しなくちゃい
けないわ。でも、日によってはもう内側にはいっているものをたっぷり
ふくらませて、何にでも触れさせるという日もなくちゃいけないわ。そ
してからだの中で感じるのよ。ときにはゆっくり時間をかけて、そうな
るのを待ってやらないと、いろんな知識がむやみに積み重なって、から
だの中でガタガタさわぎだすでしょうよ、そんな知識では、雑音をだす
ことはできても、それでほんとうにものを感ずることはできやしないの
よ。中身はからっぽなのよ。」 (p.225)
クローディアやジェイミーには、フランクワイラーのそうした忠告はきっとまだわからない。貪欲な知識欲は若いときほど旺盛であるし、好奇心も強く働く。だがそれを自分の中で消化し整理して理解しなければ何にもならないということは年齢を重ねる毎にわかってくるはずだ。それをしみじみと感じる。
いつまでも吸収するだけでなく吐き出さなければならないということ、でもそうして繭を吐き出さないうちに人は死んでしまうのかもしれない。無駄に蓄積して使われないままの知識は、堆積した無数の書物やもう開こうともしない何冊もの写真アルバムと同じように、甲斐の無い忘却の海に沈む。

The Met and Thomas P. F. Hoving
(メトロポリタン美術館の前に立つトーマス・ホビング。
彼はこの小説が書かれた当時のMetのディレクター)
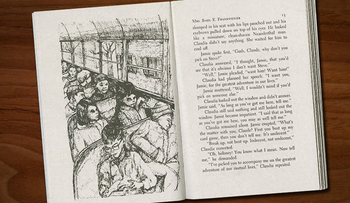
著者自身によって描かれた『クローディアの秘密』の挿絵
E・L・カニグズバーグ/クローディアの秘密 (岩波書店)

大貫妙子/メトロポリタン美術館
https://www.nicovideo.jp/watch/sm21967891
大貫妙子/ピーターラビットとわたし (live)
https://www.youtube.com/watch?v=eltLkyzwUkQ
駅から駅へ ―《関ジャム》竹内まりや特集を観る [音楽]

05月12日の夜《関ジャム 完全燃SHOW》〈竹内まりやのスゴさ〉大特集を楽しく観た。
さすがに本人が登場することはなく、本人からの取材ということだったが、それを元にした竹内まりやフリークなシンガーソングライター・さかいゆう、作詞家・zopp、評論家・能地祐子の3人を中心としたトークがなかなか面白い。
まずオキマリの好きな曲ランキング。20~50代の選んだベスト20ということなのだが、
1位 駅(1987)
2位 元気を出して(1987)
3位 不思議なピーチパイ(1980)
4位 SEPTEMBER(1979)
ああ、やっぱり〈駅〉が1位なのかと納得する。
〈駅〉は中森明菜に提供した曲、〈元気を出して〉は薬師丸ひろ子に提供した曲だが、セルフカヴァーしてむしろそのほうがヒットした自作曲である。しかし3位と4位は竹内の作曲ではない。初期のヒット曲である〈不思議なピーチパイ〉は安井かずみ/加藤和彦、〈SEPTEMBER〉は松本隆/林哲司の作品であり、3rdアルバム《LOVE SONGS》(1980) に収録されているが、年齢の高い層に最も刷り込まれている曲のようである。初期の頃は自分の曲でない、意に染まない曲を歌わせられていたことが不満だったみたいなことをどこかで読んだような記憶があるが、さすがにこのへんの大ヒット曲はそんなことはないのだとは思うけれど、ではどのへんの曲が苦痛だったのかがちょっと知りたい。でも当然ながらそういう話にはならなかった。
〈純愛ラプソディ〉を素材にした歌唱法へのアプローチ。微妙なこぶしと鼻濁音に関しての話、そしてヴォーカルがダブルで入っていることの指摘など、この部分の分析も面白い。大瀧詠一が 「まりやさんの鼻濁音が日本で一番スゴい」 と言っていたとのことだが、そう言われるととても納得できる。でも、たとえば松任谷由実には東京生まれにもかかわらず鼻濁音が無い。それはそれぞれの好みや志向もあるのだろうし、今は 「一匹、二匹、……」 という 「ひき」 の使い分けを正確にいえない人だって随分いるから、しかたがないのかなぁと嘆息する。
〈純愛ラプソディ〉に関する竹内まりやの回答というのは次のようである。
純愛ラプソディですが、実はこぶしが入るということは意識した事があ
りません。デビューの時から本能的に音が移り変わるところにちょこっ
と装飾音を入れるという歌い癖があり、それは誰かに指導されたもので
はないんです。ただ、この曲をあえてダブル歌唱で入れたのはちょっと
歌に自信がなかったからなんです。アレンジも割と穏やかなので、シン
グルでやるには強さが足りないなと自分で判断して、ダブルにしました。
ダブルって微妙にずれてるからこそ重なって聴こえる。だから言葉尻や
ビブラートの位置などを合わせていくのにすごく集中して歌いましたね。
確かにそういうのを注意して聴くと、微妙に音が変化している個所があって、本人は歌いグセと言っているし、それ自身が歌手としての味になっているのだろうけれど、全部ダブルで入れちゃったというのはやっぱりすごい。
こうした竹内まりやの回答の中で最も印象的だったのは、もちろん山下達郎との音楽的関係性、もっといえば力関係である。2人ともそれぞれ曲を作るし、かつ歌手でもあるという同業者なのだから、ぶつからないほうがおかしいと考えてしまうのが普通である。これについての回答は素晴らしく明快だった。
デモの段階で、自分の中では具体的に見えている音像がある。
それを達郎に伝えて「ここの間奏は絶対トロンボーンを入れたい」 とか
「ハーモニカがいい」 とか伝えうる限りのことは伝えて、でも達郎が 「そ
うじゃなくてこの曲はもっとこういう風にした方がいい」 という別のア
イディアを出してくることがあるのでそっちが良かったらそっちにする。
自分で見えているものは全て伝える。
コードなども、もちろん自分で決めるが、達郎が 「このコードの方がい
いんじゃない?」 と出してきても、自分の生理感にないものは元々のコ
ードに戻してもらう。というのは、それをどんどん許容していくとだん
だん山下達郎の音世界になってしまうので。達郎の音楽性と私の音楽性
は明らかに違うので。達郎自身の音楽と違う部分がある接点を持つこと
の面白さが私のプロジェクト。
サブカル出身の達郎が大事にしないといけない部分と、芸能活動から入
ってる私の世界とは、おのずと線引きがあるしファン層も違うので、で
もそれが重なり合う時の科学反応的な面白さとか、一緒にやる必然性を
音楽で感じてもらわないといけないので。
「デモの段階で、自分の中では具体的に見えている音像がある」 というのが当然だがすごい。つまり自分で編曲はしないけれどそのコンセプトは固まっているのだ。コードに関しても 「自分の生理感にないもの」 は却下というのが毅然としている。他の回答のときも、彼女は 「自分は最先端である必要はない」 と言い切っていた。自分の音楽がどうなのか、ということを知っていて、解説者が指摘していたように、あまり高い音まで無理に持っていかないという作曲理念もその一環である。
山下達郎と自分の音楽は違うという主張は当然だが、その説明の中で 「サブカル出身の達郎」 と 「芸能活動から入ってる私」 という比較の語法が、もうそのものズバリで、自分の最初の一歩は 「芸能活動」 なのだと理解しているのもすごい。それが 「意に染まなかった曲」 云々につながっているのだと思う。
人気第1位だった〈駅〉に関してはwikiにも書いてあること (山下達郎が中森明菜ヴァージョンについて否定的だったこと) だからわざわざ繰り返さないが、シンガーソングライターが他人に曲を書いた場合の機微というか、むずかしいことがあるものだと感じる。その〈駅〉の中森明菜ヴァージョンも聴いてみた。オリジナルではなく、後年のライヴ映像だが、歌の乗りにくそうな弦楽の編曲は鬱陶しさの一歩手前みたいな印象があって、いや、むしろ一歩過ぎているかもしれなくて、それに乗せて歌える中森明菜の歌唱テクニックを聴く。歌手によってその歌詞を違うふうに解釈したのだとしても、解釈が違うのは当然であり、それもまた歌詞に対する別の角度からの視点なのである。
中森明菜の〈駅〉は10枚目のスタジオ・アルバム《CRIMSON》(1986) に収録された。クリムゾンなのに黒いモノクロのジャケットで、でもそれは異なった意味のクリムゾンなのかもしれない。ちなみに相川七瀬にも《crimson》(1998) というタイトルのアルバムが存在する。もっとも相川の場合は、《Red》(1996) とか《FOXTROT》(2000) とか、もうねぇ。
実は私はそんなに竹内まりやを聴いてきたわけでもないし、山下達郎もそこそこ聴いてはいるが、全てを聴き込んでいるような聴き方ではなく、ごく普通のリスナーに過ぎない。でも今回の番組は、久しぶりにややマニアックで楽しめた。
以前住んでいた街に公営のプールがあって、でもそこは9月のはじめで営業を終えてしまう。賑わっていたプールは9月になった途端、客数が急激に減り、秋の気配がただよう。そのプールでその時期に、いつも竹内まりやの〈SEPTEMBER〉が、プアなスピーカーから繰り返し繰り返し流れていたことを唐突に思い出す。こういう曲こそが良質な歌謡曲なのだと私は思う。でもこうしたシンプルで美しかったはずのメロディは、今の時代には、もはや喪われてしまっている。それはきっと永遠に、かもしれないのだ。
竹内まりや/Turntable (ワーナーミュージック・ジャパン)

竹内まりや/Expressions (ワーナーミュージック・ジャパン)

竹内まりや/駅
https://www.youtube.com/watch?v=gjyXtpdX_Bw
中森明菜/駅
https://www.youtube.com/watch?v=ZMmHBtc60-E
番組自体をご覧になる場合は
画像は小さく音も悪いですがコレ (お早めに)
https://www.youtube.com/watch?v=mYIKg69HRUI
〈Agharta〉と〈Time After Time〉の間 ― マイルス・デイヴィス [音楽]

Cyndi Lauper (Time After Time PVより)
シンディ・ローパーの〈Time After Time〉のPVはマレーネ・ディートリヒの映画から始まる。ニッパーを抱いたシンディ。物語は始まるがそれはシンディの過去の戯画のようでもあり、すべてが幻想のようでもある。最後の、列車の窓のシーンに至るまで。
過去に、マイルス・デイヴィスのことは何回か書いてきた。《Miles in the Sky》(1968) から始まり《Bitches Brew》(1969) を経て《Agharta》(1975)《Pangaea》(1975) に至るエレクトリック・シーンは、彼の歴史の中で閉じた生態系のようにみえる。次第に進化し変貌していった手法は、進化しているように見えながら、実は停滞しているのに過ぎないのを錯視しているだけなのかもしれないと思えてしまう部分もあり、常にステロタイプに陥る危険性を併せ持っている。その頃の、あるいはその頃を回想した最近に至るまでの評価を読むと、意外に否定的な意見が散見されるのは、まさにそのステロタイプ的なルーティンであると感じてしまう方法論にあったのだと思う。
私はその頃のライヴをまとめて聴いた時期があって、それは幾つかの記事としてすでに書いたが、冷静に聴いているようにみえて、何かしらの先入観を抱いていたこともあったのではないかと今になって思う。つまりマイルスの方法論は最初から繰り返されるクリシェに過ぎないと思い、また当時のマイルスの態度が尊大過ぎるとか、PAスピーカーがうるさ過ぎた云々などと書いてあると、その場を知らない者にとっては、そうだったのかと信じてしまうものなのである。ライヴ会場での印象は実際にそうだったのだろうが、音源として聴いた場合は別の様相を帯びてくる。
《Bitches Brew》以降のライヴは後年になるほど過激になっていったが、その転換点はオフィシャルなアルバムでいうのならば《Get Up with It》(1974) から《Agharta》《Pangaea》までの2年間であり*、それはキーボードの不在によって区切られる。ギタリストが3人もいながらキーボードを弾くのはマイルス自身であって、キーボード専任のプレイヤーがいないということに意味がある。
それはシンプルに比較するのならばオーネット・コールマンの《The Shape of Jazz to Come》(1959) における2管+ベース&ドラムでピアノレスという方向性を思い出させる。
(*ピアニストの不在を正確に言うのならば、jazzdiscoのdiscography等を参照すると、ピアニストがいるのは1972年9月29日のニューヨーク、リンカーン・センターのフィルハーモニック・ホールにおけるライヴ《In Concert》のセドリック・ローソンが最後である。したがって実質的には1973年以降の3年間ということになる。《Get Up with It》に収録されているテイクも72年まではピアニストが在籍している)。
先日、なんとなく《Agharta》を聴いていたらハマッてしまった。この時期の演奏は皆同じようなものというような思い込みがあったのかもしれない。たとえば1975年1月22日の東京厚生年金ホールのライヴのブート《Live in Tokyo 1975》があるが、《Agharta》(1975年2月1日) とは明らかに違うのである。日本盤として《Agharta》を最初にリリースした際に、もちろん全公演は録音されていてそのなかから最も優れた演奏として2月1日をチョイスしたのだろうとは思う。
だがそれだけではなく、マイルスが弾くごく短いオルガンによる和音、それは曲をどこに持って行くかという一種のトリガーであり合図なのだが、その音色そのものが神秘性を帯びてしまうときがある。ギターも、それは以前にも 「よく聴くとそんなにデタラメではなくノイジーなだけではない」 とは書いたが、《Agharta》におけるリヴァーブの使い方とか、ギターとサックスの出入り、そしてそこに絡まっているポリリズムのようなものから感じ取れる印象は、すごくうまく組み上がった寄木細工のような精緻な構築物なのだ。しかしそれは物体としての形状を持ち得ない。なぜなら音楽だからである。
それゆえに、どこが優れているのかということを表現しにくい。それはごく些細な気配であり、小さな符号に過ぎない。私だけの勘違いなのかもしれない。短い一音が、その後の膨大な音群を支配する契機となることがあるのだ、と私は思う。
柴田淳のブログに、音程へのこだわりとして興味をひかれることが書いてあった。
コンピュータで歌った音を直すことは今はよくある方法なのだが、それをやるとその一瞬が自分の声で無くなるのでそれはやらない。歌い直すか、それとも何回も録音したテイクのなかから良いテイクを探すのだが、その、気になる音は 「大抵一文字なのです」 というのである (JUN SHIBATA Official site 2019年4月24日ブログ)。
ひとつの音はその曲の総体から見ればごく小さい。だがそのひとつの音が重要である場合は確実に存在する。いつでもではない。ある特定の時、地点において、重要性を持ってしまう音がある。《Agharta》に聴くのはそうした特異点の音が幾つも打ち出されることだ。
《Agharta》《Pangaea》を最後として、マイルスは長い休暇に入る。それは肉体的な疲労と病気だけでなく、尊大とも見える態度を押し通して自分の音楽を展開させたことによる精神的なストレスもあったのだろう。
1980年の復活以降、過激なスタイルは影を潜める。ポップスも取り上げ、その中で〈Time After Time〉もカヴァーされた。だがそれはあくまでジャズとしての〈Time After Time〉である。深層に流れるメロディとその上に屹立するマイルスのソロが鮮明である。《Bitches Brew》以降のエレクトリック・シーンに対して 「ロックに接近」 というような形容がされることがあるが、それは間違いであり、どこまでいってもマイルスはジャズでしかない。《Agharta》もそうである。ギタリストが3人いても、リズムがロックっぽく聞こえてもその本質はジャズでしかないし、「どうだ、ロックだろう?」 というのはマイルスの韜晦でしかない。
Miles Davis/Agharta (SMJ)

Miles Davis/Pangaea (SMJ)
![パンゲア [Blu-spec CD] パンゲア [Blu-spec CD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41Pc203ZaEL._SL75_.jpg)
Cyndi Lauper/Time After Time (PV)
https://www.youtube.com/watch?v=VdQY7BusJNU
Miles Davis/Time After Time
live in Germany 1988
https://www.youtube.com/watch?v=FpZHjvFXprk
Miles Davis/
Live in Stadthalle, Vienna, Austria, November 3, 1973.
(full)
https://www.youtube.com/watch?v=wOA9_TdRFt4
TF1のミレーヌ・ファルメール ―《Désobéissance》 [音楽]

Mylène Farmer (fashionmayann.wordpress.comより)
ミレーヌ・ファルメールの一番新しいアルバム (といっても昨年リリースなのだが) を聴いていて、その動画を探していたらまた深い沼にはまってしまった。深い森だったり深い沼だったり。
《Désobéissance》は昨年9月に発売。仏Stuffed Monkey盤で日本盤は出ていない。
音としてはエレクトロニカ風だが、それはデビューの頃からのリミックスを多く出すパターンがずっと続いているだけで、言ってしまえば永遠のワンパターンなのかもしれないが、それならPerfumeだってワンパターンなわけだし、でも本アルバムは全体に軽く仕上げられているように思う。
1曲目から4曲目までは動画をなんとか探したのだが、その後はリミックスだったりで、まぁいいや、と考えてあきらめた。
tr1の〈Rolling Stone〉は震えるようなわざと不安定なイントロで、いつも通りの暗さなのだが、でも始まってしまうとそうでもない。耳に残るリフレイン。
tr2〈Sentimentale〉はいつもとやや毛色が違っていて、声も軽く、エフェクトもかわいく作ってあるような気がする。それはこの動画にも現れていてサンチマンである。
tr3のアルバム・タイトル曲〈Désobéissance〉は音自体も映像も、王道のファルメールで、こうした建物の使い方とそこに現れる光がいつもながら上手い。ファルメールのこれまで来た道を振り返ればノスタルジックな曲ともいえる。
tr4はLPとのデュエットによる〈N’oublie pas〉。クリップは滑り台だったりブランコだったりが小道具として出てくるが、例によって画面はずっと暗い。LPはローラ・ペルゴリッジ (Laura Pergolizzi) というアメリカ人の歌手である。
だが、検索しているうちに最初の曲〈Rolling Stone〉のライヴがあった。フランスのTV局であるTF1の〈La chanson de l’année 2018〉にゲスト出演したときの映像である。(→5)
さらにFrance 2の〈JPGショー〉という番組で〈N’oublie pas〉を歌っている映像 (→6)。JPGはジェイペグではなく、ジャン=ポール・ゴルチエである。こんな番組があることを知らなかったので、一瞬、誰、このおじさん? と思ってしまったのはナイショ。ゴルチエのコレクションにファルメールがモデルとして出演したときがあって、その話をしてから歌となる。トップ画像はその2011年のショーにおけるゴルチエを着たファルメールである。
尚、7) はLa chanson de l’annéeのライヴを、近くからシロウトさんが撮ったもの。音は周囲の観客の声が入っていてめちゃくちゃだが、ダンスの動きはこの動画のほうが近くなのでわかりやすいかもしれない。
今回はリンクした動画が7本もあるので全部を観たら疲れますからご注意のほど。全部は観なくていいと思います。
Mylène Farmer/Désobéissance (Stuffed Monkey)

1)
Mylène Farmer/Rolling Stone
https://www.youtube.com/watch?v=jpsmVEiBQNQ
2)
Mylène Farmer/Sentimentale
https://www.youtube.com/watch?v=fpU4-EUErfY
3)
Mylène Farmer/Désobéissance
https://www.youtube.com/watch?v=WnRGighEBss
4)
Mylène Farmer, LP/N’oublie pas
https://www.youtube.com/watch?v=3AoS_7u9eCU
5)
Mylène Farmer/Rolling Stone
La chanson de l'année, TF1 live, le 08/06/2018
https://www.youtube.com/watch?v=MKyC8wt8HQY
6)
Mylène Farmer, LP/N’oublie pas
au JPG Show, France 2, le 13/10/2018.
https://www.youtube.com/watch?v=73OAIcq9Epk
7)
Mylène Farmer/Rolling Stone
La chanson de l'année, TF1 live, le 08/06/2018 (近くから)
https://www.youtube.com/watch?v=dhKJnq-cpl0
声もなく立ちすくむ深い森 ― マラン・マレ [音楽]

Marin Marais
最初の動機はお得な廉価盤である。しばらく前からdeutsche harmonia mundiの廉価盤を少しずつ聴いていて、前に書いたイェルク・デムスのハンマーフリューゲルによるシューベルトも《ジャーマン・ロマンティシズム・エディション》の中に収録されていた中の1曲である。
それでバッハは確かに偉大なのだけれど、だんだんその前が聴きたくなってきて、それはイタリア、フランスなどのラテン系の音楽への希求を意味する。たとえばハルモニア・ムンディのスキップ・センペのエディションだと、最初にクープランがあり、パーセルがあってブクステフーデがあって最後にバッハという選曲がなされている。
そうした興味の一環として、ラインハルト・ゲーベルがあり《Le Parnasse français》というアルヒーフ盤に気づいた。これは以前からアルヒーフでリリースされていたものだが最近はデザインを変えた廉価盤が出されている。
マルカントワーヌ・シャルパンティエ (Marc-Antoine Charpentier, 1643-1704) が私にとってのターゲットのひとりであった。シャルパンティエといってもケーキ屋さんではない。シャルパンティエという姓は比較的多いようで (つまり英語読みにすればカーペンターなので)、作曲家も複数いる。
マルカントワーヌ・シャルパンティエはいわゆるフランス・バロックだが、作品数も多く、そのジャンルも広いのにもかかわらず、まだよく知られていない作曲家のようである。とりあえず作品に振られているヒチコック番号だけで500以上が存在する。
シャルパンティエをYouTubeで検索すると《Te Deum》のPréludeばかりが出て来てしまうが、どちらかというとシャルパンティエの本質からは少し外れた元気過ぎる曲で私は頭が痛くなってしまうのだけれど、スーザだと思えば気にならなくなる。
ゲーベルのシャルパンティエにはMusique sacréeというサブタイトルが付けられているのだが、tr2からの〈Messe pour les instruments au lieu des orgues〉H 513を聴くと、歌の重要性がわかってくる。第1曲のキリエの、器楽合奏があり歌、また器楽合奏というこの唐突さは何なのだろうか。そもそもこの4曲で全曲なのだろうか。
だがシャルパンティエよりもずっと心を引きつけられたのはCD1の冒頭にあるマラン・マレであった。
マラン・マレ (Marin Marais, 1656-1728) はシャルパンティエより少し後の生まれだが、ほぼ同時代人である。作曲家でありガンバ奏者であった。たぶんシャルパンティエよりもっと不明なことの多い人だと思うが、以前に読んだクセジュの『弦楽四重奏』という本の著者、シルヴェット・ミリヨがマレの研究者であったことを思い出した (『弦楽四重奏』は→2013年05月08日ブログを参照)。
マレの〈Sonnerie de Saint Genèvieve du Mont-de-Paris〉の延々と続く異様な旋律線。それはまるで樋口一葉のつづれ織りのようでもあり、ソーサラーの呪縛による酩酊のようでもある。幾つもの変奏でなりたっているのかもしれないが、こんなに表情を変えない変奏というものがあるのだろうか。それは延々と続くチェンバロの一定したリズムによって持続されている一種のアンビエントな麻痺である。でもこの頃のバロックを聴くと、なかなか終止形に辿り着かないように聞こえてしまうこうした書法がよくあることに気付く。
同じCD1にマレの〈Sonata à la Marésienne〉も収録されているが、こちらは小さな舞曲の集成であり、構成はやや自然だ。楽譜は通奏低音の数字の書いてある形式である。
YouTubeにはマレの〈Sonnerie de……〉のゲーベルの音源もあるが、音だけなので、動画になっている木村理恵ヴァージョンをリンクしておく。同時にブクステフーデの演奏もあるが、これも長い旋律線を持った曲である。
木村理恵はバロック・ヴァイオリニストで、エマヌエル・バッハのソナタをはじめ、何枚ものアルバムがある。バロックの森は深い。

Marais: Sonata à la Marésienne
Reinhard Goebel/Musica Antiqua Köln
Le Parnasse français (Archiv)

Fantasticus XL/Conversed Monologue (Resonus Classics)

Fantasticus
(Rie Kimura, Robert Smith, Gulllermo Brachetta)/
Marin Marais: Sonnerie de Saint Genèvieve du Mont-de-Paris
https://www.youtube.com/watch?v=FAoxkVQ5NDA
Fantasticus/D. Buxtehude:
Sonate en la mineur pour violon, viole de gambe et basse continue
BuxWV 272
https://www.youtube.com/watch?v=70EFtk3vE7M
Rie Kimura, Pieter-Jan Belder/
C.P.E. Bach/Sonata in B minor, Wq 76
https://www.youtube.com/watch?v=_I58T0GaDDw



