タモリのジャズスタジオ1995 [音楽]

Wes Montgomery
YouTubeで他のものを探していたら偶然、NHKの《タモリのジャズスタジオ》という映像に行き当たった。1995年にBSで放送されたらしいがよくわからない。もちろん初めて観た。YouTubeにあるのも、飛び飛びの映像なのだが、どれを観てもそれなりに面白い。
第1回の放送はタモリと大西順子、そして林家こぶ平 (当時) というメンバーでイギリスBBCにあった古い映像を紹介してそれについて述べるという構成になっている。途中から景山民夫が参加している。
ウェス・モンゴメリーとセロニアス・モンクの映像で、これももちろん初めて観たのだが、モノクロで画質も悪いのにもかかわらず、単純にすごい。
そもそもウェス・モンゴメリーがギターを弾いている動画というのを私は初めて見たのだが、こんなふうに弾いているのか、と慄然、もうほとんど驚愕の映像である。きっと 「何をいまさら」 というジャズ通のかたがいるのだろうが、何卒ご容赦ください。
映像を見れば一目瞭然なのだが、親指で弾くというのはこういうことなのかと納得した。いや納得していないのかもしれない。普通に考えたら、あり得ない奏法である。親指で弦を弾いているのだが、人差し指から小指までの4本はギターのピックガードのあたりにかかっていて、たぶん薬指・小指あたりを中心に手をホールドさせた状態で親指であの速いパッセージを弾いているのだ。この、ギターに対しての右手の異様なポジションにびっくりしてしまう。
景山民夫はサムピックだろう、みたいなことを言っているがそれは間違いであって、あくまで親指なのだ。たぶん親指が角質化していて、原則的なストロークはダウンだがアップで弾く場合もあるように見える。ただプリングとかハンマリングも多用して、親指のダウンだけという不利な状態をカヴァーしているのだと思う。
いままで、ウェス・モンゴメリーは親指で弾くとか、オクターヴ奏法を多用する、というふうな知識はあったのだが、それは漠然とした理解と思い込みでしかなくて、こうした実物を見て納得していたのではなかったのだ。しかしそれにしても、この指の動かしかたとか、鍛錬の賜物なのだとは思うが、あり得ない。
実はいままでにもウェスの奏法を体得した、というようなギタリストの演奏を見聞きしたことはあったが、ああそういうものなのか、と思っていたのはだまされていたのだということがわかってしまった。この本家を見たことがなかったのだから仕方がないといえば仕方がないのだが。こんなふうに弾ける人はウェス本人を除いて誰もいない。まさにこういうのがジャズの巨人というのだろう。
そしてウェスの演奏だけでなく、ハロルド・マバーンのピアノのソロになってもまさに硬質のジャズの音に満ちていてこころよい。ウェスは売れるようになって、後期はいわゆるムード・ミュージック的なアルバム (A&MのA Day in the Lifeとか) まで出しているが、ああいうのははっきりいってジャズではないのだ。そういうのはたとえばナット・キング・コールなどにもいえて、彼の作品も若いときの自分でピアノを弾いている頃のほうが好ましい。
その次のセロニアス・モンクの演奏も、モンクの指使いはかなりトリッキーなのだが、ウェスの後だと、普通にしか見えない。ただ、チャーリー・ラウズはともするとあまり良い評価をされないテナーだが、この映像を見ると音もしっかりしているし、なにより立ち姿が端正である。昔のジャズ・ミュージシャンはほとんど不動の姿勢で演奏する人が多い。そういう意味では音楽へのアプローチも非常にスクエアなのだと思える。
他にも林家こぶ平 (現・正蔵) がヴォーカルはダメ、ビッグバンドもダメ、ましてグレン・ミラーなんて、などと言い切ってしまうのも面白いし、八木橋修の当時のジャズ喫茶の話もリアリティがあって引き込まれる。マイルスに対する大西順子の解説も的確で、まだジャズが音楽として元気であった頃が偲ばれる。《E.S.P.》など、ウェイン・ショーターがほとんど絵を描いて、最後にマイルスがハンコを押すとマイルスの作品になるというタモリの比喩には笑ってしまう。
10月28日の関ジャムのTV番組で、ジャンル毎にピアノはこういうふうに違うという検証のためのピアニストとして、ジャズシーンからは山中千尋が出演していたのだけれど、山中さん、やたらなグリッサンドは不要です。まぁああいう番組の方向性なんだから仕方がないかとも思うんですが。
このNHKのタモリの番組くらいのクォリティというか最低常識を求めるのは、今の時代では無理なのかもしれません。
タモリのジャズスタジオ
ウェス・モンゴメリー
https://www.youtube.com/watch?v=7DxvYTPPPJI
タモリのジャズスタジオ(つづき。でも途中で終わってしまう)
セロニアス・モンク
https://www.youtube.com/watch?v=BUcOgOr4Vmk
ガイドブック大好き ―『21世紀ブラジル音楽ガイド』 [音楽]

ガイドブックが大好きってどうなんだろう?
たとえば『サンリオSF文庫総解説』っていう本があって、サンリオSF文庫という、かつて存在した文庫について解説しているのだけれど、これを読みたいと思っても実際にはほとんど入手できないのです。良い翻訳もあったし、ちょっとこれは、っていう翻訳もあったとのことなんですが、どれがそうなのかもわからない。だって本そのものが入手できないんだから。古書店で探すときのガイドにしろ、という意味なのかもしれません。私も何冊かは持っていますが、でもほとんどは見たこともない表紙ばかり。これで、ざっとあらすじを読めば読んだ気になるかというと絶対ならない。SFファンにとってはマニアックだけれど欲求不満に陥るリストなのです。
その『サンリオSF文庫総解説』は『ハヤカワ文庫SF解説2000』、マイク・アシュリー『SF雑誌の歴史』、池澤春菜『SFのSは、ステキのS』と並んでウチの書棚にあります。なぜなら本の高さが同じだから。本の高さを揃えることは書棚に本をいっぱい詰め込むための基本技です。
さて、それらと同じ高さの本として『21世紀ブラジル音楽ガイド』という本をこの前買いました。21世紀になってからのブラジル・ポピュラー・ミュージックの、主としてCDのガイドなんですが、こういうの見てるとジャケ買いしたくなる気持ち、よくわかります。
こういうのを見ているだけで、よしこれを聴いてみたい買ってみたいと思ったのなら、本を書いた人にとっては、しめしめなリアクションなわけです。
ブラジルは南アメリカのなかで例外的なポルトガル語の国、という表現を最近知って、あ、そういえばそうだし、そういう意味では孤独な国なんだとも思いますが、ブラジルとアルゼンチンではやはり何か違う、それは言語に違いがあるからということがその要素のひとつだという説明に納得しました。
で、ブラジルってリオのカーニヴァルってことからどうしてもお祭り好きみたいな明るいイメージがあって、アルゼンチンはボルヘスだしクライバーだしピアソラだし、どうしてもそっちに惹きつけられてしまうという感じでした。ブラジルはヴィラ=ロボスとジスモンチだけれど、私のなかでは、やぱ、ちょっと弱いかな。
でも、このガイドブックを読むと、まずジョアン・ジルベルト、アントニオ・カルロス・ジョビン、そしてカエターノ・ヴェローゾの影響力っていうのはその基本になっていてすごい、という印象はあります。21世紀の音楽といいながらそれらをまだ引き摺らざるをえない。リストの冒頭にある 「+2」 (マイス・ドイス) のモレーノってカエターノの息子ですし。
ただ、ブラジルの音楽って何ていうのかなぁ、軽いんですよね。軽いから悪いとか価値が無いとかいうんじゃなくて、むしろ日本人の心にはフィットしやすいのかもしれない。ボルヘスとかピアソラとかそのへんを例にとると、スペイン語圏ってやっぱりねちっこいような気がする。あくまでも気がするのは私の感性であって、これって偏見なのかもしれませんけど。
それで先に書いたジャケ買いの話に戻るんですけれど、この本は総カラーページなので、うーん、これ何かよさそう! という気にさせます。それはこの本全体の装丁とかレイアウトにも言えるんですが、ちょっとだけヌケていて、ややダサカッコイイみたいな、そのへんの軽みがあります。あんまり考えてないのか、熟慮の上でそうなったのかがよくわからないんだけど、たぶんあんまり考えてなくて、えいっと作ってしまった手抜き加減なほうがデザインとしてカッコよかったりします。
アメリカのジャズレーベルにブルーノートっていうのがあって、昔のデザインはホントに手抜きなのがあって、でもその手抜き具合がカッコイイみたいな、もう 「あばたもえくぼ」 状態です。けれどもジャズレコードの場合は、残念ながら暑苦しい。それがブラジルデザインにはないんです。そしてそれは中身の音楽をもあらわしているように思えます。
さてもう1冊、小島智『アヴァン・ミュージック・イン・ジャパン』という、これもCDガイドなんですが、ジャンル的にくくれないというか、曖昧な、ちょっとアウトな音楽についてのリストです。前記の『21世紀ブラジル音楽ガイド』は中原仁・監修の下に複数の著者が書いていますが、この本はひとりで、しかも日本の音楽について書いていて、身近だけれどちょっと閉塞感があるのかもしれないという感じです。もちろん文章に閉塞感があるということではなくて、今の日本の音楽そのものがどんどん閉塞しているように私には感じられるんですが、それはあまりにステロタイプ化され過ぎていて、外への目が無くなってしまっている。だからブラジルの音楽なんて、まったく真逆で良いと思うんです。
小島智の選択は、いわば独断と偏見で、自分が良いと思う音楽のリストアップで、でもそういうほうが、こういうのがいいんじゃない? という主張がはっきり出ているから参考になります。だからってそれを全部鵜呑みにするわけでないことは、前のブラジル音楽と同様ですが、参考になるかならないかというのは重要で、たとえばamazonのシロウト評なんて、ほとんどは参考にならないので、なぜかといえばそれは編集がされていない状態、つまりネットの垂れ流し情報なので、それは情報としては弱いんです。ネットで見かける 「どこの歯医者が良い歯医者か」 という情報が全く役にたたない、むしろ害悪なのと同じです。
ま、ですからこの私の記事もそんなに信用してはいけない。
ランダムなんだけれど整合性がある、という一定の基準が小島智のなかにあるので、それに沿って読んでいくと大体の手がかりがつかめますのでこれは便利。あ、そうなんだ、という個所も結構あって、ざっと読んだだけですけど面白い。G-Schmittもゲルニカも取り上げられていましたので、ふむふむと読みました。ペーター・ブロッツマンの《Dear Davil》というのはちょっとマニアックかも。
ただ、ナーヴ・カッツェの項で、「サエキけんぞういわく、“日本で二番目に古いレディス・バンド (最古はゼルダらしい)」 と書いてあるんですが、wikiで調べてみるとSHOW-YAのほうがNav Katzeより古いんじゃないかな? 単純に結成年で較べてもSHOW-YAは1981年、Nav Katzeは1984年、メジャーデビューも1985年vs1991年です。そしてZERDAの結成は1979年なので確かにこれらのグループより古いですが、なんといっても奥野敦子のいたガールズ (GIRLS) がありますからね。ガールズの結成は1977年です。でもYouTubeで見たら、あんまりなパフォーマンスなので、レディス・バンドとしてカウントされていないのかもしれません (グレコのピンクのブギーが再発されているんですね。この前、見ました。ま、どうでもいいんですけど)。
残念ながらこの本、少し誤植が多いです。高橋幸弘とか、G-Schmittも最後の 「e」 は不要です。誤植の多い本って、厳しい言い方かもしれませんが、それだけで内容としての価値が下がってしまうと私は考えます。
ジャケット・デザインを見ても日本のデザインは求心的というか、やっぱり良くも悪くも日本なんだなぁと思います。どんなにやってもブラジルのアルバムのようにはならないし、逆にブラジルの人がどんなにがんばっても日本のようなデザインにはならない。色使いもそうです。『アヴァン・ミュージック・イン・ジャパン』は1色刷なので、どんな色なのかはわかりませんけれど、知っている限りはやはり日本の色ってある。だからゲルニカの《改造への躍動》みたいなのはそれを逆手にとってるからウケます。
結局、ガイドブックってカタログ文化なのかもしれないけれど、でもカタログは便利ですよね。結婚式の引き出物のカタログは味気ないけど。
21世紀ブラジル音楽ガイド (Pヴァイン)

小島智/アヴァン・ミュージック・イン・ジャパン (DU BOOKS)

Caetano Veloso, Gilberto Gil/Nossa Gente (Avisa Lá)
https://www.youtube.com/watch?v=BY4KeCak17U
ジューシィ・フルーツ/そんなヒロシに騙されて
https://www.youtube.com/watch?v=RiXU5Mj2zDM
セシル・テイラー《Poschiavo》 [音楽]

ポスキアーヴォ (Poschiavo) はスイスの南端、イタリアに突き出ている国境ぎりぎりにある町である。2016年12月の人口が3534人とあるから村と呼んだほうがよいのかもしれない。ポスキアーヴォはイタリア語読みで、wikiには各言語での読みが載っている。Italian: Poschiavo, Lombard: Pusciaaf, German: Puschlav, Romansh: Puschlav とのこと。
セシル・テイラーのアルバム《Poschiavo》はこのポスキアーヴォで1999年5月14日に行われたピアノソロによるライヴの録音である。ライヴなのだが、まるでスタジオ録音のようにクリアで残響が少なく、ベーゼンドルファーの下のほうの音が重く響いているという印象がある。といってもヘヴィなのではなくて心地よい低音であり、後期のセシル・テイラーの特徴的なピアニズムをよく捉えている。そして録音されたのは1999年であるがリリースされたのは2018年の6月であり、いわば新譜である。
1999年というと彼は69歳で、ピアニストとしてはまだまだ十分に現役だが、しかし若い頃のような目眩くように走り回る指はさすがに衰えていて、そのかわりに音の深みとか構成力に老練な味わいが出て来た頃である。よく使われるパターンというか、一種の手クセは幾つもあるのだが、その左手の重厚な打鍵とそのメロディ造形が後年になればなるほど際だってきているように思える。つまり右手はある意味オブリガートであり、重要なのは左手である。アヴァンギャルドな方向性は終始変わらないのだが、アヴァンギャルドでありながら円熟していてトリッキーなキツさがだんだんと収まってきてしまっている。それを円熟として認めるのか、それとも退行として批判するのかは自由だが、次々に繰り出されるパターンはまろやかで、尖鋭的な前衛性とか、細く過激で狷介な音楽とは無縁のようにも聞こえてしまう。
《Poschiavo》は約54分にわたる切れ目の無い1曲であり、trackも1つしかない。40’40”頃からヴォイスが混じるが、その後、一瞬ピアノの表情が変化する。延々と弾きながら飽きさせないテクニックも手練れの境地にある。
ジャズにおけるソロピアノはずっと以前からあったが、その概念を変えたのがキース・ジャレットの《Solo Concerts》であった。短い曲をピアノで弾くというそれまでの佳曲集的手法でなく、オリジナルな構想で延々と弾き続けるというコンセプトが当たったのである。そのブレーメンとローザンヌのソロが録音されたのが1973年の3月20日と7月12日、そしてリリースされたのが同年の11月とある。
この1972~1973年あたりのジャズの隆盛は凄まじいほどである。1972年はチック・コリアの《Return to Forever》が出された年であり、翌1973年はハービー・ハンコックの《Head Hunters》というアルバムが続いていることからもわかるように、世の中はフュージョンであった。
だがそうした時代でもセシル・テイラーのスタンスは変わらない。ソロによるアルバム《Indent》は1973年3月11日、オハイオでのライヴを収録したものであるが、これはキース・ジャレットのブレーメンの9日前である。つまりほとんど同時期の録音であるが、片方は大ベストセラー、もう一方は、おそらく、ごく地味にしか売れていなかったという違いがある。もちろん私が肩入れするのは売れなかったセシル・テイラーのほうである (同様にして1972年の録音ではアンソニー・ブラクストンの《Town Hall 1972》があるが、これはまさに《Return to Forever》への回答としてリリースされたものである)。
私はセシル・テイラーをそんなに聴いているわけではないので、ごくアバウトな感想なのだが、彼のソロの最も優れていると思われるアルバムは《Indent》(1973) と《Silent Tongues》(1974)、そして1976年の《Dark to Themselves》と《Air Above Mountains》だろう。そしてユニットにおける最高傑作として1978年の《One Too Many Salty Swift and Not Goodbye》を偏愛している。
当時の日本では、1973年5月22日に東京厚生年金会館で行われたライヴを収録したトリオレコードの《Akisakila》がそれなりの評判になったのではないかと思われる。演奏曲目は〈Bulu Akisakila Kutala〉の1曲だけで、同時期にソロピアノの《Solo》というアルバムもリリースされているので、《Indent》よりもこれらの録音のほうが先にリスナーの耳には届いたのではないだろうか。wikiには《Indent》のリリースが1973年とあるが、Sessiongraphyには1977年と表記されていて、どちらが正しいのか不明である。たぶん1977年のように思えるが、調べてもわからなかった。そしてSessiongraphyも最近は更新されていないので、この《Poschiavo》のデータはもちろん収録されていない。
《Poschiavo》はアリゾナのBlack Sunというレーベルから出されているが、ブラック・サンのサイトを見ると《Indent》と《Silent Tongues》も別ジャケットで再発しているようである。だが、amazon.comにはあるけれどamazon.co.jpを含めた国内のサイトにはBlack Sun盤は見つからない。
Cecil Taylor/Poschiavo (Black Sun Music)

The 2013 Kyoto Prize Workshop in Arts and Philosophy
Cecil Taylor and Min Tanaka
https://www.youtube.com/watch?v=Q8rqVi_ROSo
intoxicateを読む [音楽]

タワーレコードに『intoxicate』という宣伝誌があるんです。宣伝誌とか言っちゃいけないのか。じゃ、フリーマガジン。でもそういうのがあることを最近まで知らなかったというのは一生の不覚! ってほどのものでもないんですが、これ、すごいんです。何といっても無料です。無料なのにものすごく内容が濃い。無料でこんなものを配ってしまってよいものなのか、と心配してしまうくらいです。もっとダメダメな有料の音楽雑誌ってあるようなないような。
CDショップにはもうひとつ大手の店があります。実店舗でもネットショップでも、タワーと並び立つ店、といえばわかると思いますけど、そこの宣伝誌はCDなどを注文すると同梱されてくるので便利なことは便利。
ところが、内容的にはほとんどがJ-popのチケットガイドなんですよね。全然ダメってわけではないですけど、私にとって有用な情報ではないので、ふ~んと目を通しておしまい。
対する『intoxicate』は店舗に行かないと手に入らないという難易度があるんです。難易度って言ってしまうのはいけないんだけど、つまりネットショップで全てを済ませようとするのはよくない、ということを改めて感じたわけ。実はタワーレコードにはそれ以外でも店舗にしかない品物とかあって、つまりネットでは買えないけど店に行くと買えるということがありましたので、うーん、タワーってなかなかやるじゃん、と思うのです。ホントに欲しいモノは苦労して手に入れるもんなの、という教訓です。
で、今回の『intoxicate』136号は表紙がヒキョーです。映画《モリのいる場所》のスチルを使っているんですが、この猫は何? 右下にハメコミ合成のようにいる個性的な猫。すごいなこの写真。この宣伝誌、ちがった、フリーマガジンを手にとらせようとする意欲が見えます。
内容は表紙にも使われているのでもわかるように、まず、樹木希林の近作の映画の話題を手際よく纏めてあってとても好感が持てます。私はほとんど映画を観ないので《東京タワー》という映画ももちろん観ていませんが、キャストを見たらこれすごいじゃん! と今さら言うのって何年遅れてるんだ、と顰蹙をかうこと必至な感想です (正確に言うのなら映画を観ないんじゃなくて、映画館に行くのが億劫なんです)。
他にもDENONからBeyond the Standardというシリーズで出されるアンドレア・バティストーニ/東京フィルでの武満徹の《系図》の語りを、のんがやっていることについての経緯が詳しく書かれていて、購入意欲を誘われます。買うかどいうかというとそれはまた別の問題ですけど。
そうそう。昔、プロコフィエフの《ピーターと狼》をピーターがナレーションしたのがありましたね……関係ないか。
シテ・ド・ラ・ミュジークでブーレーズ・ビエンナーレという記事もとても興味深く読みました。ブーレーズ先生とバレンボイムとの関係性が面白いです。
というか、こういう話題ってそんなにたいしたことではないのかもしれないんだけれど、ネットが普及してきたんだからそういう情報がどんどん入ってくるかというと、かえって入ってきていないような気がするんですよね。情報というのは必要としないと入ってこないもので、そしてネット社会というのはどうしても低きに流れるような気がして、もっといえばネット鎖国なので、それはアナログレコードの時代とデジタルのCDの時代の関係性に似てます。どういうことかというと、アナログで必要とされない作品はCDにならない。どんどん廃盤になって、それはもう無かったのと同じことになる。どうしても欲しくても、ボロボロのジャケットの中古のアナログ盤しかなくてそれが何万円もしたりする。つまり 「売れ線」 でないものは淘汰されるということです。私は 「売れ線」 なものにはほとんど興味がないので、こういうのは困るんです。
その点でこの『intoxicate』を読んでいて少しは溜飲が下がったというか、まだまだ骨のあるヤツはいるもんだ、と思いました。
もちろん宣伝誌ですから、CDとかDVDとかブルーレイなどの紹介が各記事の末尾についていますが、価格が表記されていません。すごく不親切です。つまり、買う人は価格が幾らだろうが買うし、買わない人はたとえ10円でも買わないということを示しているんだ、と私は思いました。だから不親切でいいんです。
内容について詳しいことはここに載っていますのでどうぞ。
http://mikiki.tokyo.jp/articles/-/19394
というか、興味を持たれたらタワーレコードに行きましょう。これだけ宣伝したらタワレコから何かくれないかな? ダメか。
で、私がホントに興味を持った情報もあったんですが、それは今後のブログネタに使うので秘密です。そういう意味でもとっても便利なフリーマガジンです。
モリのいる場所・トレーラー
http://mori-movie.com
日々是好日・トレーラー
http://www.nichinichimovie.jp
David Bowie/Peter and the Wolf
https://www.youtube.com/watch?v=kpoizq-jjxs
タイムマシンにおねがい ― サディスティック・ミカ・バンド [音楽]
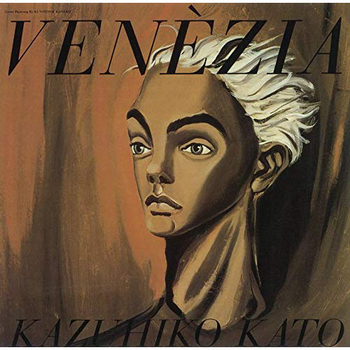
YouTubeを探してみると、加藤和彦をキーワードにしてみても出てくるのは〈あの素晴らしい愛をもう一度〉ばかりなのだ。教科書にも載っているし、世間的な評価とは、そういうものなのかもしれないのだけれど。以前の記事と重複するのだが、あらためて加藤和彦について書こうと思う。
加藤和彦 (1947.03.21-2009.10.16) は《パパ・ヘミングウェイ》(1979)、《うたかたのオペラ》(1980)、《ベル・エキセントリック》(1981) という、いわゆるヨーロッパ3部作が最もすぐれていると言われるが、残念ながらその動画は今、YouTubeの中では見つからない。もっとも私が聴いた加藤和彦はもっと後の《ヴェネツィア》(1984) が最初だ、ということは以前に書いた。それさえも後追いで聴いたのだが、ヨーロッパ3部作を経て、《あの頃、マリー・ローランサン》(1983) の次の《ヴェネツィア》、そのデカダンな表情は持続していて変わらない。ヴィスコンティに倣うようにヴェネツィアはいつまでも憂いの都市なのだ。
《うたかたのオペラ》はベルリンをテーマにしているが (つまり《Low》から《heathen》に至るデヴィッド・ボウイを連想してしまうが)、そのジャケットには L’opéra fragile というタイトルが読み取れる。「うたかた」 はボリス・ヴィアンが描いたような écume でなく fragile なのだ。
大貫妙子への編曲や、ちわきまゆみへの提供曲など、そこから聞こえてくるのは憂鬱な想念と遠い瞳である。そうした退嬰の音こそが聴きたい音なのであって、かつて坂本龍一が 「この熱情的な暗さは」 みたいなことを言っていたように覚えているが、それは多分に病み上がりの、身体に力が入らないときに聴く、いつもと違うような印象に感じられてしまう音楽に似て、決して爽やかで、ときにほの暗いフォークソングではない。
もちろん加藤和彦の音楽活動の最初はフォーク・グループから始まったのではあるけれど、ドノヴァンの影響があることからも、それはアメリカンなフォーク・ソング・スタイルをルーツとしていないことがわかる。ドノヴァンの音にはサイケデリックがベースとして存在するが、もっとルーツを辿っていけばそれはスコットランドの暗い倦怠である。そしてサディスティック・ミカ・バンドのコンセプトはグラムでもありポップでもあるが、その精神性はきっとパンクなのだ。
加藤のソロアルバムはデカダンであるがラグジュアリーであり、決してパンクでもグラムでもなく、バンドに対するスタンスとはかなり異なる。それゆえに時々バンドに還ることがリフレッシュとして必要だったのかもしれない。
だがそれよりも、種々雑多な提供曲の彩りに驚いてしまう。それだけ才能に恵まれていたのかもしれないが、それでいてどの曲にも加藤和彦がいて、その個性は比類がない。自然に 「しるし」 は現れ、その穏やかな音の表情が空間を満たす音楽を支配する。でもそうした 「お仕事」 が本来の音楽的思想の基盤を消耗させてしまったのかもしれないとも思う。
サディスティック・ミカ・バンドは結成から解散まで1972~75年の4年間しかないが、その後も何回か再結成されている。どこまでをサディスティック・ミカ・バンドと称するかによって差があるが、とりあえず3回結成されたというふうに考えるのが自然だろう。今回、調べていたらドラムは初めから高橋幸宏ではなく、最も初期にはつのだ☆ひろが在籍していたことを知った。後期のジャックス、渡辺貞夫など、つのだの活動の幅広さと存在感に驚いてしまう。
ミカ・バンドの最大のヒット曲は〈タイムマシンにおねがい〉である。ミカ、桐島かれん、そして木村カエラと、歌手を変えた3つのヴァージョンがある。桐島かれんの時期のアルバム《天晴》(1989) の最初の曲〈Boys & Girls〉というタイトルは、ブライアン・フェリーのアルバム《Boys and Girls》(1985) を意識しているように思える。音楽のトレンドもロキシー後の爛熟した時代だったように感じる。
ライブ・イン・トーキョー (1989年04月09日) における桐島かれんのヴォーカルは、ぶっ飛んでいて、各メンバーも元気でなかなか見せる。大村憲司のギターも鋭角的だ。ファッションがバブルっぽいこと、そして流行だったのかもしれないスタインバーガーの使用など、いかにもその当時を彷彿とさせる映像である。
そして長い時を経て、木村カエラを歌手に迎えたのが最後のミカ・バンドであるが、私はその最後のミカ・バンドしか知らない。だが〈タイムマシンにおねがい〉はもはやスタンダード曲になっていたから、そういう曲があることは知っていた。
YouTubeを探すと、ミュージックステーション (2006年10月27日) と、NHKホールでのライヴ (2007年03月08日) の動画がある。どちらも木村カエラの歌唱はシャープで屈託がなく、煌めいている。この最後の時期に、かろうじて私は伝説ともいえるミカ・バンドの歴史に追いついた。それまでそれは私にとって未知の領域だった。しかしやっと追いついた時、すでにゴールは過ぎていたのかもしれない。この日のNHKホールの異様なほどのホールの雰囲気と高まりは結果として突出したピークであり、やがてグラフはゆるやかに下降してノイズに埋もれることになる。そしてそれは本当に最後の、ミカ・バンドの輝かしき終焉であった。
サディスティック・ミカ・バンド/Live in Tokyo
(コロムビアミュージックエンタテインメント)

サディスティック・ミカ・バンド/Big Bang, Bang! (木村カエラ)
ミュージックステーション 2006.10.27.
https://www.youtube.com/watch?v=9CnBhmcmx20
サディスティック・ミカ・バンド/タイムマシンにおねがい (木村カエラ)
NHKホール 2007.03.08
https://www.youtube.com/watch?v=HyNpr7Zyucs
サディスティック・ミカ・バンド/タイムマシンにおねがい (木村カエラ)
PV 2006
https://www.youtube.com/watch?v=LBpoOCeQC7k
サディスティック・ミカ・バンド/タイムマシンにおねがい (桐島かれん)
東京ベイNKホール 1989.04.09
https://www.youtube.com/watch?v=ZO_czc4v8Cs
サディスティック・ミカ・バンド/タイムマシンにおねがい (ミカ)
orginal 1974
https://www.youtube.com/watch?v=b8ATGykcyYg
高中正義バンド/タイムマシンにおねがい (ミカ)
虹伝説 II, Live at Budokan: 日本武道館 1997.09.05
https://www.youtube.com/watch?v=RjraqYb2EbQ
北畠美枝/だいじょうぶマイ・フレンド
(わざとオリジナルでない歌唱をリンクしておく)
https://www.youtube.com/watch?v=6IR3skMdjl8
まだらの腕 ― 深緑野分『ベルリンは晴れているか』を読む [本]

読みながら最初に思い出したのはフルトヴェングラーがハーケンクロイツの下でワーグナーを指揮している映像だった。芸術が歪んだ目的に利用された好例であり、一見整然とした演奏会のようでありながら、その時代の恐ろしさを垣間見せる映像。
『ベルリンは晴れているか』は戦後すぐのベルリンを舞台にした物語。その間に幕間として戦時中の主人公のクロニクルな過去が挟まれる。冒頭から全く弛緩の無い展開にどんどん引き込まれる。ほんの少しの時間でも読み進めたい小説というのは滅多にないが、その滅多にないような小説を久しぶりに読んだ気がする。
『ベルリンは晴れているか』というタイトルはルネ・クレマンの《パリは燃えているか》を連想させるが、内容はヘヴィであり、冷静にナチスの恐怖政治とその後の疲弊した混乱のベルリンを描いている。
以下に出版社のサイトにある簡単なあらすじを引用する。
1945年7月。ナチス・ドイツが戦争に敗れ米ソ英仏の4ヵ国統治下にお
かれたベルリン。ソ連と西側諸国が対立しつつある状況下で、ドイツ人
少女アウグステの恩人にあたる男が、ソ連領域で米国製の歯磨き粉に含
まれた毒により不審な死を遂げる。米国の兵員食堂で働くアウグステは
疑いの目を向けられつつ、彼の甥に訃報を伝えるべく旅立つ。しかしな
ぜか陽気な泥棒を道連れにする羽目になり――ふたりはそれぞれの思惑
を胸に、荒廃した街を歩きはじめる。
ミステリ仕立てになっているが、基本的には歴史小説的であり、ミステリではないと私は思う。あえてミステリだとするならばその手法は、ある有名なミステリ作品のプロットに似ている (この本をすでに読んだ人はコメント欄等でそれをバラさないように)。そしてドイツの戦中戦後の歴史を非常によく調べているのがわかるし、あまりにもドキュメンタリー風に読めてしまう部分があって、読み進めるのを躊躇うほどである。日本人作家がここまでドイツの歴史を読み込んで書けるのか、ということに対しては逆に、ドイツ人でなかったからこそ書けた、書いてしまえたという論理が成立するのだと思う。
ストーリーの中で重要な役目を果たしているのは黄色い1冊の本で、それはエーリッヒ・ケストナーの『エーミールと探偵たち』(Emil und die Detektive, 1929) の英訳本である。主人公の少女アウグステが英語を学ぶきっかけとなった本であり、アウグステの手から本は何度も失われるが奇跡的に戻ってくる。それだけでなくケストナーがナチスの時代には焚書の対象であったこと、そして焚書の対象から免れていた児童文学である『エーミールと探偵たち』がベルリンを舞台とした物語であることなど、幾つもの意味がその本に籠められている。
不良の少年たちと出会い、木炭車で移動したり、無理矢理カエルを食べさせられたりする場面は、まさに児童文学的なワクワク感に満ちているのだが、その輝きは一瞬のことで、すぐに暗い現実がのしかかる。
また固有名詞として、ジードルング (1920年代にドイツで建築された集合住宅)、フラクトゥーア (ナチス時代に好まれた飾り文字)、ユンクメーデルブント (少女団)、レーパーバーン (公認売春街) など、興味深い言葉に惹かれる。
ナチスが行ったこと、そしてドイツ人に対しての指摘と断罪は、NKVD (ソ連の秘密警察) のドブリギン大尉の言葉に端的に表れている。
大尉はにやりと唇を歪ませ、紫煙を吐いた。
「フロイライン、あなたも苦しんだのでしょう。しかし忘れないで頂き
たいのは、これはあなた方ドイツ人がはじめた戦争だということです。
“善きドイツ人”? ただの民間人? 関係ありません。まだ『まさかこ
んな事態になるとは予想しなかった』と言いますか? 自分の国が悪に
暴走するのを止められなかったのは、あなた方全員の責任です」 (p.239)
深緑野分とマライ・メントラインの対談の中で、メントラインは次のように語っている。
日本人が戦争を考えるときにドイツに価値がある点は、日本がただでさ
えグレーなものをよりグレーにして曖昧にしてきたのに対して、ドイツ
の場合はアウシュヴィッツを見てもわかるように、言い訳のきかない極
端なことを現実にやってしまったことにあると思います。
(ちくま/2018年10月号。以下同)
曖昧にしてきたことというのは端的に言ってしまえば、A級戦犯に全ての罪を押しつけ、われわれ国民は被害者だったという日本人の言い訳に対しての否定である。それに関連してブルンヒルデ・ボムゼルの《ゲッベルズと私》の映画に対しても言及しているのだが (ボムゼルはゲッベルズの秘書だったが、そのインタヴューで 「ホロコーストに関しては知らなかった」 と述べたという)、メントラインは、
どうも日本では映画で描かれたボムゼルさんはちょっと可哀想という捉
えられ方だったらしいけど、私から見てそれはありえないですね。日本
だと大学教授でも浪花節的な同情論に染まってしまうイメージがありま
す。ドイツのインテリ層はそれがなくて 「なぜこの人は平気で矛盾した
ことを言うんだろう」 と考える。
これに対して深緑は、やはり自分も日本人的な思考をしていて、「“理解ができるのでは” というところから入ってしまい、「この人は何が悪かったのか」 みたいな分析より理解を優先させ」 てしまうと応じているのだが、これに対してメントラインは 「分析から入るとSFになって、例えばP・K・ディックの『高い城の男』でナチス幹部を 「こいつらの本質はこうだ」 と並べて説明する感じになってしまいがちな気がする」 と言う。
ボムゼルの述懐のドキュメンタリーと、ハンナ・アーレントが最近再認識され、たとえば『イエルサレムのアイヒマン』が再版されているのには関連性が存在するように思う。そしてメントラインの、分析的な手法の限界という指摘は鋭い。
だが、偉そうなことを言っていたドブリギン大尉には彼なりの野心があって、結局彼は粛清されてしまうのだが、それはソヴィエト (=ロシア) という国のメタファーでもあり、ナチスとは異なった意味での恐怖政治が存在していることは自明である。
『ベルリンは晴れているか』では単にナチスの対ユダヤ人政策、つまり人種差別だけでなく、男性優位な思想、障碍者や同性愛者への差別なども描かれていて、そのどれもが過去のドイツの戦争で起こったことだと過去形で語るだけではその本質を理解したことにはならない。それは現代にも同様に通用している真正の鏡のようでもある。
深緑野分/ベルリンは晴れているか (筑摩書房)

オペラ座2007年のアズナヴール [音楽]
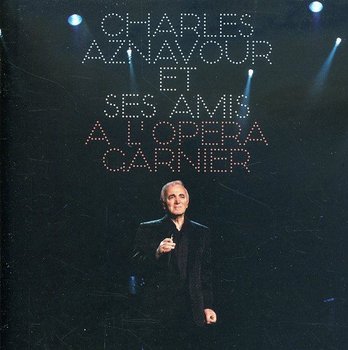
シャルル・アズナヴール (Charles Aznavour, 1924-2018) について、私は語るほどの知識を持っていない。だが先月の日本公演は最後の来日というキャッチで宣伝されていたが、日本における最後の公演であるだけでなく、文字通りの最後の公演となってしまった。
私にとってのアズナヴールの印象は否定的な意見から始まる。それは私のフランス語の教師がアズナヴールやアダモが嫌いだったからで、レオ・フェレやジョルジュ・ブラッサンスは良いけれどアズナヴールやアダモなんてダメという、いまから考えれば偏向なのだが、というより単に自分の信条を含めた嗜好を投影したものに過ぎなかったのだろうが、シャンソンなどロクに知らないまだ未熟で若い私はそれをそのまま信じてしまってそれが刷り込まれてしまっていた。
そのことに限らずアンチな人々の意見には、アズナブールは通俗だとか、さらにはシャンソンにおける北島三郎だとか、いろいろとかまびすしい。だが、入門者向けのシャンソン・ベスト盤のようなアルバムがかつての東芝EMIから出ていて、それはリーヌ・ルノーから始まるようなわかりやすい名曲選だったのだが、そうしたオーソドクスな選曲に親しんで繰り返し聴いていた身には、通俗こそその時代のトレンドを感じるのには好適だし、真実の姿を知る方法だと思ってしまうのである。
たぶんTVで観たアズナヴールのライヴの記憶がある。たぶん、というのはTVでなくヴィデオ映像だったのかもしれなくてはなはだ曖昧な記憶なのだが、そんなに熱心に観ていたのでなかったのだが、はっとするような曲があった。だが具体的な曲名とか歌詞とかが浮かばなくて、抽象的な記憶しか残っていないのだが、もし同じ曲を聴けばわかるはず、と曖昧なままにしてしまったのだけれど、今あらためてYouTubeなどで探してみてもどうしてもわからない。アズナヴールは膨大な録音があるのだから、具体的な手がかりがないとほとんど無理なのである。
そうして探しているうちに、目的とは違うのだけれども、幾つか心に残る曲を見つけた。そのうちの1曲、〈2つのギター〉は2007年のオペラ座でのライヴである。L’Opéra Garnier はオペラ座とかパレ・ガルニエとかいろいろな呼び方をされるし、団体としてのパリ国立オペラをオペラと呼称することもあるが、その客席はステージからの視点で撮された映像ですぐにそれとわかる古風で印象的な構造をしている。
アズナヴールの映像は《Charles Aznavour et ses amis à L’Opéra Garnier》というタイトルのCDとDVDがリリースされているが、そのDVDからの映像であると思われる。だがこれは例によってPALで、そのため日本ではほとんど流通していないようだ。アズナヴールには普通のフォーマットのDVDで出されているものもあるのだが、これはそうではないのが残念である。
浅倉ノニー氏のサイトをいつも拝読させていただいているが、それによれば〈2つのギター〉のルフランの歌詞はアルメニア語というよりボスニア語に近いのだそうで、しかしアズナヴールの精神的なルーツであることは確かだ。ギターはジプシーの弾くギターをあらわしていて、その音は故郷への郷愁であるとともに人生への郷愁を暗示する。
シャンソンはドラマである、と誰かが言っていたのを覚えている。歌手は短い1曲の間にドラマを演じ、そして死ぬ。人生も長いドラマであるのかもしれないが、シャンソンはそれを凝縮した標本なのかもしれないのだ。言葉と、音楽と、仕草と、歌われている劇場の空気と、すべてがうまく合わさったとき、それは美しい稀有なひとときを形成するが、一瞬にして崩れてゆく。映像は記録として残るがその実体はすでに消滅している。それゆえに音楽は、幾ら具体的な歌詞で歌われようとも、どこまでも抽象的なものでしかない。
アズナブールベスト40 (ユニバーサルミュージック)

Charles Aznavour/Les deux guitares
à l’Opéra Garnier 2007
https://www.youtube.com/watch?v=Z24X730KABU
コンサートの全容はこの映像だが画質はあまりよくない
https://www.youtube.com/watch?v=kQ7kE9vgDjE



